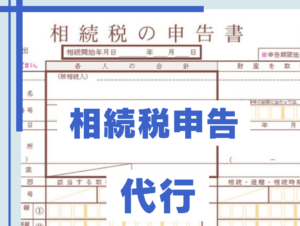「相続って何から手をつければ…」「相続税の申告、難しそう…」 大切な方を亡くされた悲しみの中で、手続きの不安まで抱えるのは本当につらいですよね。でも、ご安心ください。相続税申告はポイントを押さえれば、決して乗り越えられない壁ではありません。
この記事では、相続税申告が初めての方でも「まず何をすべきか」がすぐに分かり、スムーズに行動に移せるよう、重要なポイントをギュッと凝縮して解説します。
この記事を読めば、これだけは分かります!
- 相続税申告が必要かどうかの判断基準
- 相続税申告の全体の流れ(7つのステップ)
- 各ステップで「あなたがやるべきこと」
さあ、不安を少しでも軽くして、最初の一歩を踏み出しましょう。
【最重要】相続税申告、あなたは必要?「基礎控除額」をチェック!
まず、相続税の申告が全員に必要なわけではないことを知っておきましょう。カギとなるのは「基礎控除額」です。これは「この金額までなら相続税はかかりませんよ」という非課税枠のこと。
基礎控除額の計算式
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
- 法定相続人とは?:法律で決められた相続人のこと。主に配偶者、子(子がいない場合は孫)、親(親がいない場合は祖父母)、兄弟姉妹の順です。
- (例) 故人の相続人が配偶者と子供2人(計3人)なら、基礎控除額は4,800万円 (3000万円 + 600万円×3人)。 この場合、相続財産の合計が4,800万円以下なら、原則、相続税の申告も納税も不要です。
まずは故人の財産(預貯金、不動産、株など)がどれくらいあるか、大まかに把握しましょう。 もし基礎控除額を超えそうなら、申告が必要になる可能性大。申告と納税の期限は、原則として「亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。早めの準備が大切です。
相続税申告7つのステップ:これだけ押さえればOK!
相続税申告は、大まかに以下の7ステップで進みます。
- 遺言書はあるか?
- 誰が相続人か?
- 財産はどれくらいか?
- どう分けるか?(遺産分割協議)
- 税金はいくらか?(相続税額の計算)
- 書類を提出(申告書の作成・提出)
- 税金を納める(納税)
各ステップで何をするのか、具体的に見ていきましょう。
【ステップ1】遺言書はあるか?
- あなたがやること: 故人が遺言書を残していないか探します(自宅、公証役場など)。
- ポイント:
- 遺言書があれば、原則その内容に従って遺産を分けます。
- 遺言書(自筆証書遺言で法務局保管制度を利用していないもの)は、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。勝手に開けないようにしましょう。
【ステップ2】誰が相続人か?
- あなたがやること: 故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本を集めます。
- ポイント:
- これらで法的な相続人を確定します。
- もし故人に多額の借金がある場合、「相続放棄」(相続開始を知ってから3ヶ月以内)も検討が必要です。
【ステップ3】財産はどれくらいか?
- あなたがやること: 故人の全財産(預貯金、不動産、株式などのプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も)をリストアップし、「財産目録」を作ります。
- ポイント:
- 生命保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」として課税対象ですが、一定額まで非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)があります。
- 不動産や非上場株式などの評価は複雑なため、税理士などの専門家に相談するのが安心です。
【ステップ4】どう分けるか?(遺産分割協議)
- あなたがやること: 相続人全員で、誰がどの財産をどれだけ相続するかを話し合います。
- ポイント:
- 全員が合意したら、その内容を「遺産分割協議書」という書類にまとめ、全員が署名し実印を押します。印鑑証明書も必要です。
- この書類は、不動産の名義変更や預金の解約、相続税申告の際に必要です。
【ステップ5】税金はいくらか?(相続税額の計算)
- あなたがやること: 各相続人が取得する財産に基づいて、納めるべき相続税を計算します。
- ポイント:
- ここは非常に複雑で専門知識が必要です。多くの方が税理士に依頼します。財務省のデータによると税理士に相続税申告を依頼される方の割合は約86%と言われています。
- 配偶者には「配偶者の税額軽減」(最大1億6千万円または法定相続分まで非課税)という大きな控除があります(この特例を使うには相続税の申告が必要となりますので、注意が必要です。)。その他にも未成年者控除、障害者控除など、税負担を軽くする制度がありますが、適用には条件があります。
- 無理に自分で計算しようとせず、まずは専門家に相談することを強くおすすめします。
【ステップ6】書類を提出(申告書の作成・提出)
- あなたがやること: 相続税申告書に必要事項を記入し、集めた書類(戸籍謄本、遺産分割協議書、財産評価の資料など)と一緒に税務署に提出します。
- ポイント:
- 提出先は「故人の最後の住所地を管轄する税務署」です。
- 提出期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
【ステップ7】税金を納める(納税)
- あなたがやること: 計算された相続税を納付します。
- ポイント:
- 納税期限も申告期限と同じく10ヶ月以内です。
- 原則として現金で一括納付ですが、難しい場合は分割(延納)や物納(不動産などで納める)といった方法も、条件を満たせば可能です。これらも税務署や税理士に相談しましょう。
困ったら専門家(税理士)に相談しよう!
ここまで読んで、「やっぱり難しそう…」と感じた方もいるかもしれません。特に財産の評価や税額計算は、専門家でないと難しい部分が多いのが実情です。そんな時は、相続税に詳しい税理士に相談しましょう。
税理士に依頼するメリット
- 正確な申告: 複雑な計算や書類作成を任せられ、ミスを防げます。
- 節税の可能性: あなたに合った特例や控除を的確に活用し、納税額を抑えられる可能性があります。
- 時間と手間を削減: 面倒な手続きから解放され、精神的な負担も軽くなります。
- 税務調査への対応: 万が一、税務調査があっても安心です。
税理士選びの簡単なポイント
- 相続税案件の経験が豊富か。(年間、税理士が経験する相続税申告の件数は1件と言われています。年間10件以上あれば安心だと言えます。)
- 親身に話を聞いてくれ、質問しやすいか。(税理士もサービス業です。話しやすさなどの相性をみて決めましょう。)
- 「二次相続」まで見据えた提案をしてくれるかどうか?(配偶者が相続する場合の次の相続を「二次相続」といいます。一次相続で特だったとしても、二次相続で損してしまうケースもあります。)
- 関連する専門家との連携体制(相続税申告だけでなく、相続登記や預金の解約手続きも対応できる体制になっているか?)
- Googleのクチコミ(評価がいいところを選びましょう。)
おわりに:最初の一歩を踏み出そう
相続税申告は、確かに手間と時間がかかる手続きです。しかし、一つひとつのステップを順番に進めていけば、必ず完了できます。
この記事を読んで、「まず何をすればいいか」が少しでも明確になったでしょうか。まずは「基礎控除額の確認」「戸籍謄本を集めてみる」「財産を大まかにリストアップしてみる」など、今日できることから始めてみてください。
そして、決して一人で抱え込まず、分からないことや不安なことは、早めに専門家の力を借りることも考えてみましょう。それが、スムーズで円満な相続への近道です。