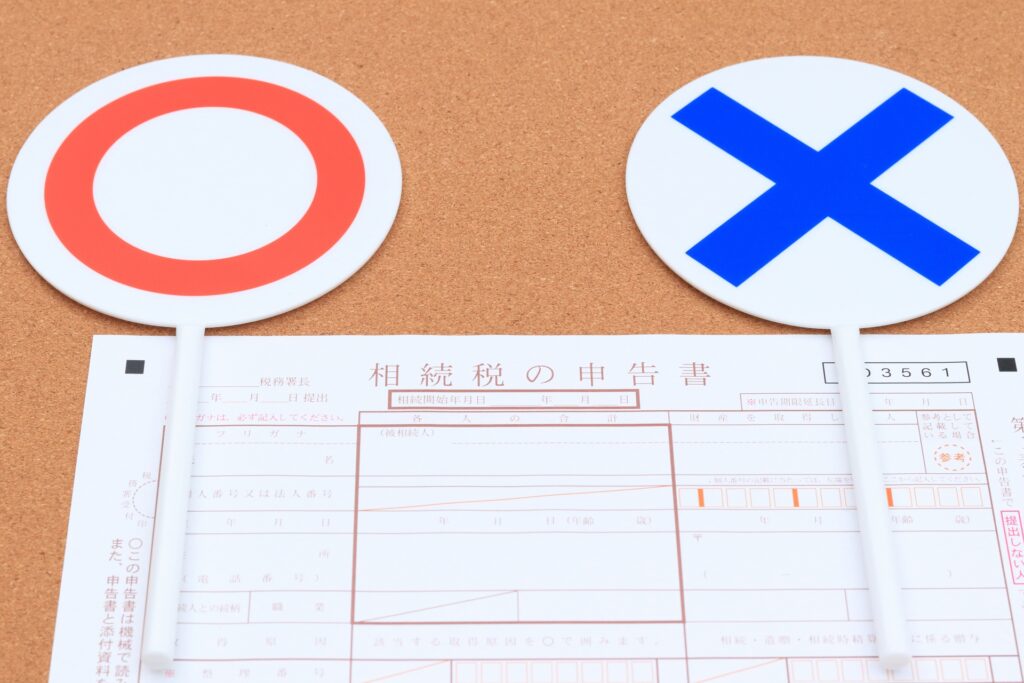
「相続した遺産に相続税がかからないなら、申告も不要でしょ?」そうお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は、相続税がかからない場合でも、税務署への申告が必要なケースがあります。この点を誤解していると、後で思わぬペナルティが課される可能性もあるため、注意が必要です。
国税庁の調査によると、亡くなった被相続人の数に対して相続税が課税されるのは毎年8~9%程度であり、令和5年度(2023年)の課税割合は9.9%です。つまり、約9割の人は相続税が課税されないという実態がありますが、それでも「申告義務」の有無は慎重に判断しなければなりません。この記事では、相続税の申告が「不要」になるケース、「義務」として申告が必要なケースを分かりやすく解説します。ご自身の状況がどこに該当するか、ぜひご確認ください。
1. 相続税の申告が不要になるケース
相続税の申告・納税が不要となるのは、主に以下の二つの状況に該当する場合です。
1-1. 遺産の総額が「基礎控除額」以下になる場合
相続税の申告が不要となる最も基本的なケースは、相続する財産の総額が、相続税の「基礎控除額」を下回る場合です。この場合、相続税は課税されず、申告も不要となります。
基礎控除額の計算方法 基礎控除額は、以下の計算式で算出されます。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例えば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円となります。相続財産がこの4,800万円以下であれば、相続税はかからず、申告も必要ありません。
基礎控除額は法定相続人の数によって変動するため、正確な人数を把握することが重要です。民法で定められた法定相続人には、以下の順位があります。
- 配偶者: 必ず法定相続人となります。内縁関係の人は含まれません。
- 第1順位: 子(養子や離婚した元配偶者との実子も含む)。子が亡くなっている場合は孫が代襲相続人になります。
- 第2順位: 直系尊属(父母、祖父母など)。第1順位の相続人がいない場合に限ります。
- 第3順位: 兄弟姉妹。第1・第2順位の相続人がいない場合に限ります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪が代襲相続人になります。
遺産総額を計算する際には、現金や不動産だけでなく、みなし相続財産や生前贈与された財産も考慮に入れる必要があります。
- みなし相続財産: 生命保険金や死亡退職金などが該当します。これらには「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。この非課税枠を差し引いた結果、遺産総額が基礎控除額以下になる場合も申告は不要です。
- 相続開始前一定期間内の贈与財産: 被相続人が亡くなる前の3年以内(2027年1月1日以降は段階的に7年以内)に相続人が受けた生前贈与は、相続財産に加算して相続税を計算します。
1-2. 特定の控除を適用した結果、税額が0円になり、かつ申告義務がない場合
相続税の課税価格が基礎控除額を超えていても、以下の控除制度を適用することで相続税額が0円となる場合は、相続税の申告が不要です。これらの控除は、特例と異なり、適用するための申告義務がありません。
- 障害者控除:相続人が85歳未満の障害者である場合、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)を相続税額から差し引くことができます。相続人の税額から引ききれない場合、その扶養義務者の相続税額から控除することも可能です。
- 未成年者控除:相続人が18歳以下(令和4年3月31日以前の相続については20歳以下)の未成年者である場合、18歳になるまでの年数1年につき10万円を相続税額から差し引けます。これも障害者控除と同様に、扶養義務者の税額から控除できる場合があります。
- 相次相続控除:10年以内に続けて相続が発生した場合に、税負担を軽減する制度です。前回の相続で課税された相続税の一部を今回の相続税額から控除できます。
- 外国税額控除:国外で課せられた相続税がある場合に、その金額を日本の相続税額から差し引くことができます。
- 贈与税額控除:被相続人の死亡から3年以内(2027年1月以降は段階的に7年以内)の生前贈与や、相続時精算課税制度を利用した贈与において支払った贈与税を、相続税額から差し引くことができます。これらの控除を適用した結果、相続税額が0円になる場合は、申告は不要です。
2. 相続税がゼロ円でも申告が「義務」となるケース
「相続税がゼロ円なら、申告も不要」という考え方は間違いです。特定の特例や税額控除を適用することで相続税がゼロ円になる場合は、税務署がその特例の適用状況を把握するため、相続税申告書の提出が義務付けられています。申告を怠ると、特例の適用を受けられず、本来は発生しなかったはずの相続税を支払うことになります。以下に該当する特例・控除を適用する際は、必ず申告が必要です。
2-1.配偶者の税額軽減を適用する場合
配偶者が相続した財産が1億6,000万円、または法定相続分相当額までであれば相続税はかかりません。しかし、この特例の適用には、申告することが義務付けられています。
2-2.小規模宅地等の特例を適用する場合
被相続人の居住用や事業用宅地の評価額を最大80%減額できる特例です。この特例の適用によって相続税がゼロ円になるケースは少なくありませんが、適用には所定の書類を添付した相続税申告が必須です。添付資料の詳細については、下記のPDF資料をご参照ください。
【(参考) 相続税の申告の際に提出していただく主な書類】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2018/pdf/10.pdf

2-3.相続財産を公益法人等に寄付した場合の非課税特例を適用する場合
相続財産の一部を国や地方公共団体、特定の公益法人等に寄付すると、一定の要件を満たせば寄付した財産が非課税になります。しかし、控除を受けるためには、申告期限までに寄付した財産の明細書など、所定の必要書類を添付した相続税申告が必要です。
2-4.その他の特例
- 農地の納税猶予の特例
- 特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例
- 非上場株式等についての納税猶予の特例(法人版事業承継税制)
- 個人の事業用資産についての納税猶予及び免除の特例(個人版事業承継税制)
- 医療法人の持分についての相続税の税額控除の特例。
これらの特例も、適用には相続税申告書の提出が求められます。
遺産分割が未確定の場合の注意点 :申告期限内に遺産分割がまとまらない場合でも、上記の特例を適用するためには対応が必要です。その際は、いったん法定相続分で相続したと仮定して相続税を申告・納税し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出します。その後、3年以内に遺産分割を完了し、改めて申告し直すことで特例の適用を受けられます。
3. 相続税申告の要否を判断する際の注意点
相続税の申告が必要かどうかの判断は、非常に複雑であり、間違いはペナルティにつながる可能性があります。以下の点に注意して確認しましょう。
3-1.見落としている相続財産はないか
タンス預金、電子マネー、仮想通貨、海外口座の預金、キャッシュレス決済アプリの残高、ゴルフ会員権など、認識されていない財産があるかもしれません。被相続人が亡くなる前の3年以内(2027年1月以降は段階的に7年以内)の生前贈与財産も確認が必要です。
3-2.基礎控除額の計算ミス
法定相続人の数の誤りや、養子、離婚した元配偶者との実子などの扱いに注意が必要です。正確な人数は戸籍謄本等で確認しましょう。
3-3.「亡くなった人の財産だけ」で考えない
みなし相続財産(生命保険金や死亡退職金)や、相続開始前一定期間内の生前贈与財産、名義財産(名義上は別人(例えば子や孫)になっているが、実質的には被相続人の財産とみなされる預金や保険などの財産)も課税対象となりこれらを含めて遺産総額を計算する必要があります。
3-4.ボーダーラインギリギリの判断
正味の遺産額が基礎控除額とほぼ同額で判断に迷う場合は、念のため申告をしておくことをお勧めします。後から財産が見つかった場合、期限後申告よりも修正申告の方がペナルティが軽くなるためです。
3-5.申告が不要でも、その他の相続手続きは必要
相続税申告が不要でも、相続人が複数人いる場合には、遺産分割協議、遺産分割協議書の作成、不動産を被相続人が所有している場合には、不動産の相続登記(令和6年4月1日から義務化)、そのほかの手続きとして、銀行口座の名義変更・解約、車や株式の名義変更、健康保険や年金の手続き など、多くの手続きが必要になります。これらの手続きを怠ると、後々トラブルに発展する可能性があります。
4. 申告しない場合のペナルティと税務調査
「相続税申告が必要なのに、申告しなかった」という場合、加算税や延滞税などの重いペナルティが課される可能性があります。
- 無申告加算税:申告期限までに申告書を提出しなかった場合に課されます。自主的に期限後申告書を提出すれば税率を低く抑えられますが、税務署に指摘されてからでは税率が上がります。
- 延滞税:納付期限までに納税しなかった場合に課される利息に相当する税金です。
- 重加算税:財産を意図的に隠したり、偽ったりした場合に課される非常に重いペナルティです。無申告加算税に代わって課されることがあり、税率も高くなります。
税務調査と「相続についてのお尋ね」 税務署は、被相続人が亡くなった事実や、KSKシステム(税務署のシステム)に蓄積された膨大なデータから、相続税申告が必要な人をある程度把握しています。
- 「相続についてのお尋ね」:相続開始から6~8ヶ月後に、税務署から「相続税についてのお尋ね」が届くことがあります。これは税務調査の事前通知ではありませんが、相続税申告書の提出を促す目的で送付されます。申告が不要な場合でも、必要事項を記入した「相続税の申告要否検討表」を提出して、その旨を伝えるべきです。
- 税務調査:税務署は、追徴税額が大きいと見込まれる無申告事案に重点的に税務調査を行います。税務調査の対象に選定された場合、税理士に相談し、自主的に期限後申告書を提出することが最も良い選択肢となります。
5. 相続税申告の期限
相続税の申告期限は、原則として「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。納付も同日までに完了させる必要があります。この期限を過ぎてしまうと、前述のペナルティが課されるため、十分な注意が必要です。
6. 相続税申告を不要にするための生前対策
相続税の申告を不要にする、あるいは相続税額を軽減するための生前対策も有効です。贈与税の非課税特例などを活用し、生前に財産を贈与することで、将来の相続財産を減らすことが可能です。
- 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与):婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産やその取得資金の贈与があった場合に最大2,000万円まで贈与税が非課税になります。
- 住宅取得等資金の非課税の特例:親や祖父母などから住宅取得資金の贈与を受けた場合に最大1,000万円まで贈与税が非課税になる特例。
- 教育資金の一括贈与:30歳未満の子または孫が、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた際に最大1,500万円まで贈与税が非課税になる特例。
- 結婚・子育て資金の一括贈与:直系尊属から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合に、最大1,000万円まで贈与税が非課税になる特例。
これらの特例には要件があり、適用を検討する場合は専門家への相談が推奨されます。
7. 相続税の申告で迷ったら、税理士法人とおやまにご相談ください
相続税の申告が必要かどうかの判断は、遺産の評価方法、特例や控除の適用条件など、専門的な知識を要する複雑なプロセスです。自己判断で誤った結果を招くと、本来発生しなかったはずの税負担やペナルティが発生するリスクがあります。
税理士法人とおやまは、相続に関するお客様のお悩みに寄り添い、適正な価格で透明性の高いサービスをご提供いたします。
- 相続税の申告義務があるか分からない
- 遺産の評価方法に不安がある
- 複雑な特例の適用を検討したい
- 相続手続き全般について相談したい
- 税務調査への対応に不安がある
など、どのようなお悩みでも、まずは税理士法人とおやまにご相談ください。無料相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
この記事の監修税理士

税理士法人とおやま
税理士 遠山 大地
東京・高田馬場で、相続税申告と相続対策に特化した税理士をしております。これまで300件以上の相続税申告に携わってまいりました。豊富な経験と専門知識を活かし、お客様の大切な財産を次世代へ円滑に引き継ぐお手伝いをいたします。
相続は、人生において大きな節目となる出来事です。相続税の手続きは複雑で専門的な知識が求められるため、多くの方が不安を抱えていらっしゃいます。
お客様一人ひとりの状況に寄り添い、分かりやすく丁寧なご説明を心がけておりますので、相続に関するお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

