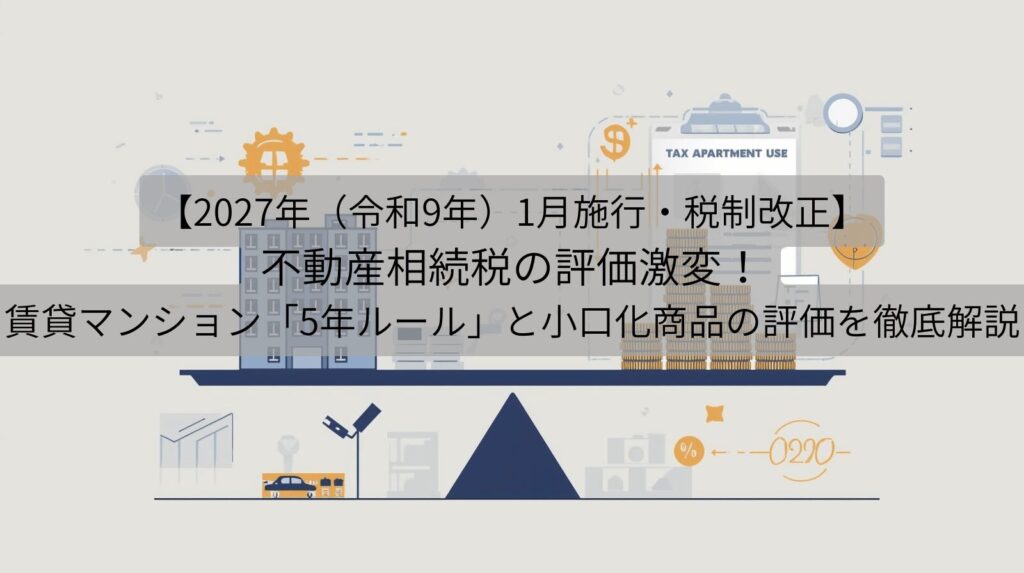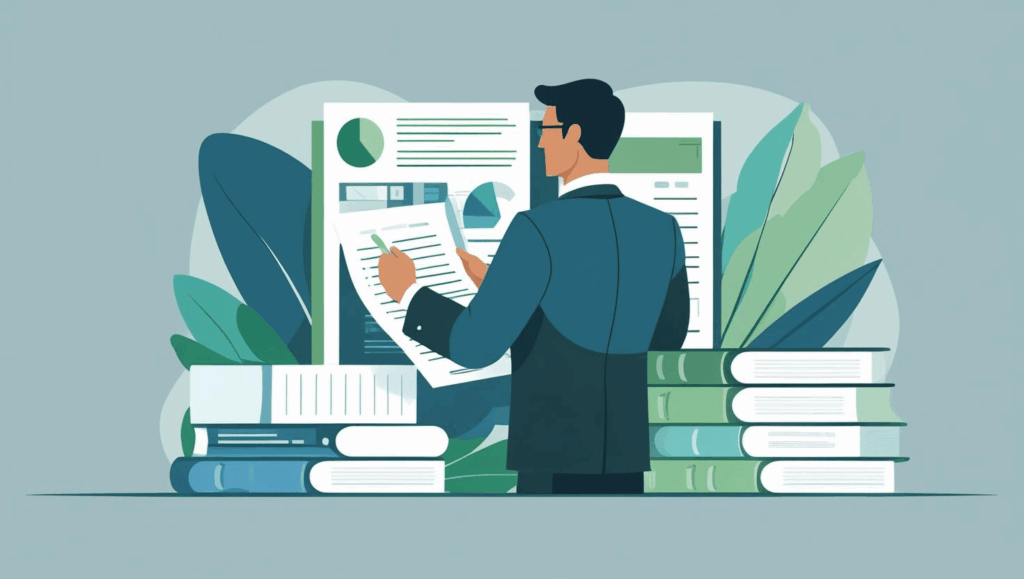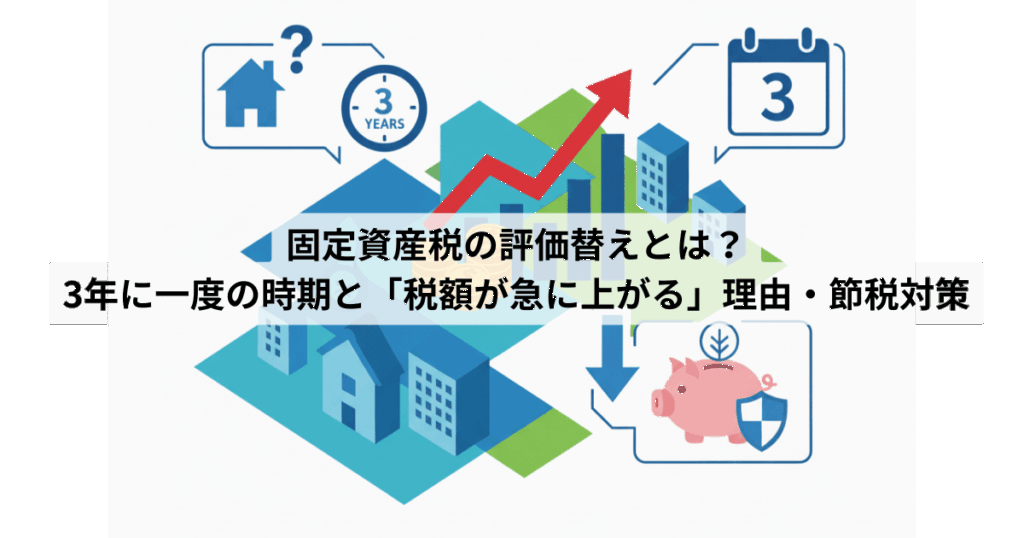
固定資産税は、土地や建物を所有する限り毎年課税される地方税です。 その税額の基準となる「評価額」は、3年ごとに見直される「評価替え」の制度によって決定されます。
「評価替え」の年になると、ご自身の不動産の評価額が変わり、それに伴い課税額が変動する可能性があります。
この記事では、固定資産税の評価替えの基本的な仕組みとタイミング、税金が上がる原因、そして適切な税負担とするための専門的なチェックポイントについて解説します。
1. 固定資産税の評価替えの基本:3年に一度の原則と目的
固定資産税は、「適正な時価」すなわち評価額を基準として課税されるものです。本来であれば、資産価格の変動に合わせて毎年度評価を見直すことが、納税者間の公平に資するとされています。
しかし、日本全国の膨大な量の土地や家屋について、毎年評価額の見直しを行うことは実務上不可能であり、また評価事務の簡素化や課税コストの抑制の必要性から、原則として土地と家屋の評価額は3年間据え置かれる制度が取られています。
この3年間の資産価格の変動に対応し、均衡の取れた適正な価格に見直す作業が「評価替え」です。
1-1.基準年度と評価据え置きのルール
評価替えが行われる年度を「基準年度」と呼びます。
- 基準年度(評価替えが行われる年): 賦課期日である1月1日時点の価格に基づき、評価額の算定替えが行われます。
- 第2年度、第3年度(据え置き年度): 原則として新たな評価は行われず、基準年度の価格がそのまま据え置かれます。
直近の評価替え(基準年度)は令和6年度(2024年度)に実施されました。このため、次回の評価替えは令和9年度(2027年1月1日時点)に実施される予定です。
| 令和6年度(2024年度) | 評価替え |
| 令和7年度(2025年度) | 据え置き |
| 令和8年度(2026年度) | 据え置き |
| 令和9年度(2027年度) | 評価替え |
| 令和10年度(2028年度) | 据え置き |
| 令和11年度(2029年度) | 据え置き |
| 令和12年度(2030年度) | 評価替え |
1-2.評価替えの例外的な変更
原則として3年間据え置かれますが、基準年度以外でも以下のような特別な事情がある場合は、新たに評価が行われ、価格が決定されます。
- 土地の地目の変換や家屋の増改築、損壊など、物理的な変更があった場合。
- 新たに固定資産税の課税対象となった土地や家屋。
- 据え置き年度(令和7年度、令和8年度など)において、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないと判断された土地(地価動向を反映し価格の修正が行われる)。
なお、償却資産(事業用の資産)については、土地や家屋とは異なり、所有者が毎年1月1日現在の状況を申告し、毎年評価が見直されます。
2. 「地価が下がっているのに税金が下がらない」原因
お客様から「地価公示が下がったと聞くのに、どうして固定資産税は下がらないのか?」というご質問をよくいただきます。税額が下がらない、または上昇してしまう主な原因には、評価替えの仕組みや特例措置の終了が関わっています。
2-1.負担調整措置による是正過程
固定資産税では、税負担の公平性を確保するため、「負担調整措置」という制度が講じられています。
この措置の目的は、地域や土地によって評価額に対する税負担に格差を生じさせないよう、「負担水準」(前年度課税標準額を評価額で割った割合)の均衡化を図ることにあります。
地価が下落している場合でも、現在までの課税標準額が本来負担すべき税額に比べて低い土地(負担水準が低い土地)については、課税の公平性を是正する過程として、課税標準額をゆるやかに引き上げていく仕組みとなっています。
そのため、地価が下落し評価額自体が下がっていたとしても、負担水準の影響で固定資産税額は必ずしも下がるとは限らず、むしろ上昇する場合があるのです。
2-2.軽減措置(特例)の適用終了
税額が急激に上がる二つ目の原因は、特定の軽減措置の適用期間が終了することです。
新築住宅は、一定の要件を満たすと、初めて固定資産税が課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火住宅などは5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。この期間が終了すると、本来の税額に戻るため、急に税金が高くなったと感じられます。
2-3. 住宅用地の特例の解除
土地にかかる固定資産税では、住宅が建っている土地(住宅用地)に対して「住宅用地の特例」が適用され、課税標準額が大幅に減額されます。
しかし、住宅を取り壊したり、住宅以外の用途(駐車場など)に変更したりした場合、この特例が適用されなくなり、税額が急激に高くなります。また、近年問題となっている「管理不全空家」や「特定空家」に指定された場合も、同様に特例が解除され、固定資産税が約6倍になる可能性があるため、注意が必要です。
3. 固定資産税の税負担を軽減する特例制度
固定資産税には、一定の条件を満たすことで税負担が軽減される、以下のような特例や減額措置が設けられています。
3-1.住宅用地の特例
住宅の敷地として使用されている土地については、その面積に応じて課税標準額が軽減されます。
- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分): 固定資産税が6分の1に、都市計画税が3分の1に軽減されます。
- 一般住宅用地(200㎡を超える部分): 固定資産税が3分の1に、都市計画税が3分の2に軽減されます。
3-2.新築住宅の減額措置
新築された住宅(令和8年3月31日までに新築されたものなど、適用条件あり)は、一定期間、固定資産税が2分の1に軽減されます。
- 一般の住宅:新築後3年間適用。
- 3階建以上の耐火・準耐火住宅:新築後5年間適用。
3-3.既存住宅の改修に伴う減額措置
既存の住宅について、耐震改修や省エネ改修を行った場合も、一定期間、固定資産税の減額措置を受けられる可能性があります。これらは工事完了後の申請が必要です。
4. 固定資産税の評価額を確認し、将来の税金対策へつなげる
固定資産税は3年ごとに評価が見直されますが、その評価額が適正かどうかは、不動産を所有する方にとって非常に重要な問題です。特に不動産の評価は、相続税対策にも間接的につながります。
4-1.評価額の見直しの機会
納税義務者は、毎年4月頃に設けられる「固定資産税課税評価額の縦覧期間」を利用して、自身が所有する不動産の評価額が適正か、近隣の土地の評価額と比較し確認することができます。
万が一、この縦覧によって評価額に誤りが見つかれば、将来にわたって税額を減らすことができるほか、固定資産税の還付が認められる場合もあります。申告漏れ等による通常の還付手続きは5年、市区町村のミスによるものは最長20年など一定期間分しか還付されないため注意が必要です。そのため、早めに確認することが重要となります。
4-2.土地と家屋の評価における「誤り」
固定資産税の評価額は、市町村(東京23区は都税局)が決定しますが、その算出過程において誤りが生じる可能性がゼロではありません。
- 家屋の評価 :建物の評価額は、定められた建築単価に用途や構造、施工の質などによる評点を振り分けて算定されますが、この評点付けの過程でミスが発生することが多いとされています(例:単純な計算ミス、用途の見間違い、主観による過剰な評点など)。
- 土地の評価 :土地の評価は、路線価や各種補正法(画地計算法)に基づき一貫した手法で行われるため、単純なミスは少ない傾向にあります。しかし、外見からは発見しづらい利用単位分けの誤りや、非課税資産の切り離し、実測面積の採用といった細かい評価誤りが見受けられることもあります。過去には、市が定める評価基準に定められた減価が織り込まれていなかったために、対象者全員に大型還付が認められた事例もあります。
5.まとめ
固定資産税の評価額に疑問を感じた場合、それはご自身の不動産価値と税金について改めて考える良い機会と言えるでしょう。
固定資産税の評価額は、相続税申告における不動産評価の基礎ともなる重要な指標です。私たち税理士法人とおやまは、相続の専門家として、不動産評価に関する豊富な知識と経験を有しております。
特に相続税の申告では、土地の形状や周辺環境、法的な制約などを多角的に分析し、適正な評価額を算出することが極めて重要です。この評価は税理士の専門性によって大きく変わり、当法人ではお客様の状況を丁寧に精査し、土地の評価額を大幅に減額した実績もございます。
固定資産税をきっかけに、将来の贈与や相続まで見据えた不動産の税金対策を検討してみてはいかがでしょうか。不動産に関する税金や、将来の相続についてご不安な点がございましたら、ぜひ当法人の初回無料相談をご利用ください。