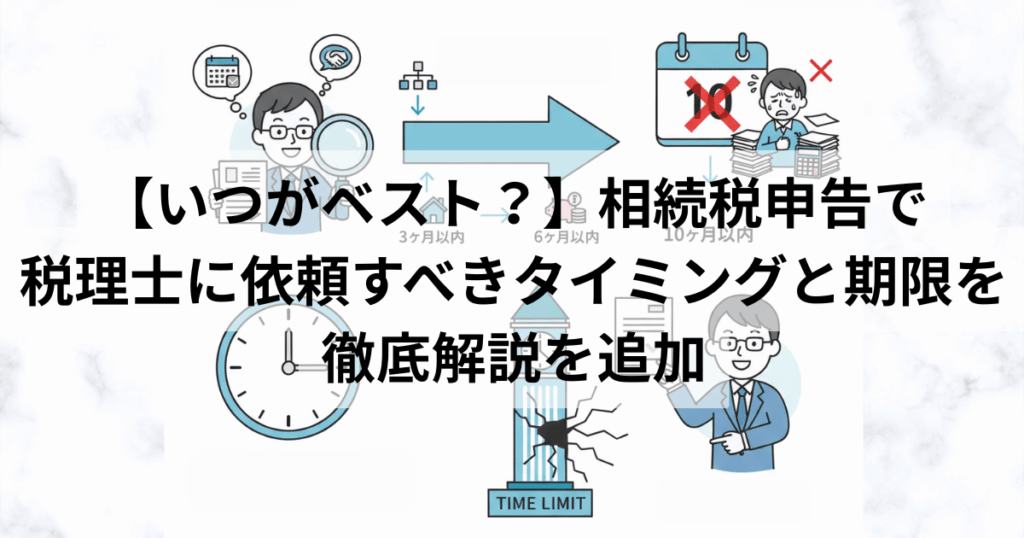
大切なご家族を亡くされた後、ご遺族は葬儀や法要、各種手続きに追われる日々を過ごします。その慌ただしい中で、相続税申告の期限は着実に迫ってきます。相続税の申告と納税には、被相続人(亡くなった方)が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内という厳格な期限が定められています。
この10ヶ月という期間は、遺産分割協議なども並行して進める必要があるため、決して余裕があるわけではありません。期限に間に合わないと、思わぬペナルティが発生する恐れがあります。
相続を円満に、かつ適切に終えるためには、どのタイミングで税理士に相談し、依頼するのが最も効果的なのでしょうか。本記事では、相続税申告における税理士への依頼タイミングと、申告をスムーズに進めるためのポイントを解説します。
1.相続税申告は「10ヶ月」が期限!期限までにやるべきこと
相続税の申告・納付期限は、原則として被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。申告先は、相続人の住所地ではなく、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署となります。
この10ヶ月の間には、葬儀や法要などの準備で最初の2ヶ月程度があっという間に過ぎてしまうことが多いです。税理士が申告をお手伝いする期間はおよそ6ヶ月間とされ、一般的に前半の4ヶ月で財産の確定作業を行い、後半の2ヶ月を遺産分割協議の期間として割り当てるのが理想とされます。
期限内に完了させるべき主な手続きには、次のものが含まれます。
| 手続き | 期限 | 備考 |
| 相続放棄または限定承認の確定 | 死亡を知った日から3ヶ月以内 | 負債が多い場合に検討。家庭裁判所への申し立てが必要。 |
| 準確定申告 | 死亡を知った日から4ヶ月以内 | 被相続人に所得がある場合(事業所得、不動産所得など)に必要。 |
| 遺産分割協議 | 遅とも9ヶ月以内を目安 | 相続税の特例適用のため、申告期限(10ヶ月)までに協議を済ませる必要がある。 |
| 相続税の申告と納付 | 死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内 | 申告書を作成し、税金を納付する。 |
準確定申告の期限(4ヶ月)や、相続放棄・限定承認の期限(3ヶ月)は、相続税申告の期限(10ヶ月)よりも短いため、特に注意が必要です。
2. 税理士に相談・依頼すべきベストなタイミング
税理士に相続税申告の相談をするタイミングは特に決まりはありませんが、各種手続きには期日があるため、できるだけ早い方が不利益を被る可能性が低くなります。
2-1. 相続発生前:節税を最大化する生前対策のタイミング
最も早いタイミングは、相続が発生する前、つまり生前対策の段階です。 生前に相談することで、以下のような大きなメリットが得られます。
- 節税の選択肢が格段に広がる:何年も前から相談しておけば、生命保険の非課税枠の利用、贈与、不動産の将来的な特例適用、将来の相続税シミュレーションなど、時間をかけた適切な対策(タックスプランニング・ライフプランニング)が可能です。
- 遺産分割や納税資金の検討:生前に家族構成や財産の状況を共有することで、円満な遺産分割や納税資金の確保について、事前に検討・準備できます。
- 相続税が発生することが明らかな場合:明らかに相続財産が多く、相続税が多額になることが分かっている場合は、発生前に相談することが特に推奨されます。
2-2. 相続発生後:四十九日法要後が目安
相続が発生した後の相談は、一区切りついた四十九日法要を終えてからが、ご家族の気持ちも落ち着き、手続きを開始するのに良いタイミングとされています。あるいは、四十九日の前に税理士などの専門家と話をしておき、相続人が集まる四十九日という機会に手続きを開始するのも有効です。
2-3. 遅くとも守りたい期限:4ヶ月以内、最低でも3ヶ月前
相続税の申告を期限内に間に合わせ、特例を適用するためには、税理士への依頼は早ければ早いほど良いですが、どんなに遅くとも以下のタイミングまでには相談を開始すべきです。
- 死亡から4ヶ月以内 :相続税の申告をスムーズに進めるため、亡くなってから4ヶ月以内を目安に税理士に相談することをお勧めします。このタイミングであれば、戸籍収集や財産評価をスムーズに進めることができ、遺産分割協議にも十分な時間を確保できます。また、相続税申告に注意を向けがちですが、不動産所得などがある方は準確定申告の期限(相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内)があるため、延滞税などの罰金をかけずに申告をしたい場合には、この期限を守る必要があります。
- 申告期限の3ヶ月前(死亡から7ヶ月後)まで: 申告期限に間に合わせるためには、遅くとも期限の3ヶ月前(死亡から7ヶ月後)までには相談するのが必須です。税理士は膨大な資料確認、財産評価、計算を行う必要があり、時間が必要だからです。なお、この時期から相続税報酬に特急料金加算が付いてくる税理士事務所が多いです。特急料金加算は事務所によって異なりますが、通常の報酬に+30%~が一般的です。
3. 税理士への依頼が遅れることの深刻なリスク
相続税の申告は、自分でできる場合もありますが、期限に余裕がない状況で不慣れな手続きを進めると、大きな不利益を被る可能性があります。
3-1. 税額を安くできる特例が使えなくなる
相続税の特例(例えば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など)を適用するためには、原則として申告期限までに遺産分割協議が成立していることが要件となります。
遺産分割協議が申告期限までにまとまらない場合(未分割申告)は、一旦特例を適用せずに納税し、後日協議がまとまってから修正申告や更正の請求を行うことになります。この手続きは二度手間になるだけでなく、当初の納税額が大きくなる可能性があり、延納の可否など納税資金の問題が生じるケースもあります。
3-2. ペナルティの発生
申告期限に間に合わないと、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されてしまいます。また、申告内容に誤りがあり過少申告が発覚した場合は、過少申告加算税や重加算税が発生するリスクもあります。
3-3. 財産評価に時間がかかる
相続財産に不動産が多く含まれる場合、その評価には時間がかかります。特に、以下のようなケースでは、評価に相当な時間を要し、申告期限に間に合わないリスクが高まります。
- 土地区画整理事業対象地、特定路線価を付す必要がある土地など、個別の評価額の申出が必要な土地。
- 非上場の自社株が含まれる場合。
- 土地の形状が複雑な場合や角地の場合など、路線価や倍率表だけでは評価できない場合。
経験豊富な税理士であれば、不動産の現地調査を行い、土地の形状などを精査することで、評価額を下げて最大限の節税を実現できる可能性があります。
3-4. 費用が増加する可能性がある
申告期限が近い場合や、未分割申告後に修正申告や還付請求が必要になった場合など、手続きが複雑化すると、税理士費用が追加で発生する可能性があります。早いタイミングで相談することで、お客様の費用負担を抑えることができます。
4. 相続税に強い税理士を選ぶためのポイント
相続税の申告は、税理士であれば誰に依頼しても同じではありません。依頼する税理士によって納税者の負担は大きく左右されるため、相続税に強い税理士を選ぶことが重要です。
相続税に強い税理士の条件には、以下のような点が挙げられます。
- 相続税申告の実績が多い:相続税申告を5年以上扱っており、年間10件以上の実績があれば、相続税に強いと言えます。
- 不動産の現地調査に強い:書面だけでなく現地調査を行い、評価額を下げる方法を模索することで、最大限の節税に繋げられます。
- 二次相続まで見据えた提案ができる:一次相続だけでなく、将来の二次相続まで見据えた遺産分割の提案を受けることで、合計税額を抑えることが可能です。
- 他の士業との連携が取れている:弁護士や司法書士など、他士業との連携体制が整っており、ワンストップで相続に関する様々な問題に対応できること。
- 税務調査への対応力がある:相続税は税務調査が入りやすい税目であり、税務調査を意識した申告書を作成できること(書面添付制度の利用など)が重要です。
相続手続きを始める際は、まず税理士に相談し、申告の要否、遺産分割、申告、納税までのひととおりの流れを聞いてみることが推奨されます。
相続税申告なら、実績豊富な「税理士法人とおやま」へ
相続税申告をどの税理士に依頼すればよいかお悩みなら、ぜひ「税理士法人とおやま」にご相談ください。40年の経験と1000件を超える相続税申告の実績で、お客様をサポートします。
「税理士法人とおやま」が選ばれる理由
- 専門家による高品質な申告:経験豊富な相続の専門家と国税庁OB税理士が、税務調査を意識した高品質な申告書を作成します。
- 不動産評価による節税:現地調査を徹底し、土地の評価額を適正に見直すことで、相続税の減額を実現します。
- ワンストップ対応:弁護士・司法書士など他士業との連携により、相続に関するあらゆる問題を一括でサポートします。
- 柔軟な相談体制:土日・夜間・Web面談に対応。ご家族の都合に合わせてご相談いただけます。
- 緊急対応も可能:申告期限1週間前といった緊急のご依頼に対応した実績もございます。諦める前に、まずはご連絡ください。(※追加料金が発生する場合や、状況により対応できない場合もございます。)
相続に関する初回のご相談は無料です。大切なご家族を亡くされ、不安を抱える中で複雑な手続きを進めるのは大変なことです。お客様の心に寄り添い、円満な相続の実現を全力でお手伝いいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

