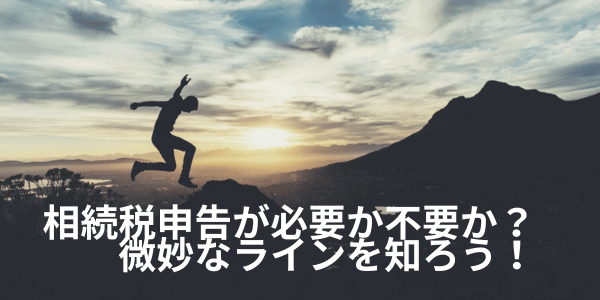「相続税の申告って、一体いつ必要なの?」「基礎控除ってなに?」「節税対策ってできるの?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、相続税の基礎知識をわかりやすく解説します。基礎控除額の計算方法や、相続税の申告が必要となるケース、そして相続税に関する疑問を解消できるよう、丁寧にご説明します。
相続税の申告に不安を感じている方や、相続について初めて学ぶ方でも、この記事を読めば、相続税の全体像を把握することができます。
相続税申告が不要なケース
相続税申告が必要かどうかは基礎控除を超えるかどうかによって変わっていきます。
基礎控除とは?
基礎控除とは、相続税を計算する際に、一定の金額を控除することができる制度です。この制度により、相続税の負担を軽減し、遺族の経済的負担を軽減することが目的です。相続税は、亡くなった方(被相続人)が残した財産に対して課税されますが、すべての財産が課税対象となるわけではありません。
基礎控除額の計算方法
基礎控除の額は、以下の計算式に基づいて算出されます。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
例えば、法定相続人が3人いる場合、基礎控除額は次のようになります。
3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円
この基礎控除額を超える遺産がある場合にのみ、相続税の申告が必要になります。
基礎控除額以下であれば申告不要!
基礎控除額以下の遺産額であれば、相続税の申告は不要です。
例えば、遺産の総額が4,800万円以下であり、法定相続人が3人の場合には、相続税の申告義務はありません。この基礎控除制度は、相続税の負担を軽減し、多くの家庭で申告の手間を省くために設けられています。
相続税申告が必要となるケース
基礎控除を超える場合
基礎控除額とは、 相続税の計算において、一定の金額まで非課税とされる金額のことです。法定相続人の数によって変化し、3,000万円に法定相続人一人あたり600万円を乗じた金額が基礎控除額となります。相続財産の総額が、この基礎控除額を超えた場合は、相続税の申告が必要となります。
特例の適用がある場合
配偶者の税額軽減
配偶者が相続した場合、一定の金額までは相続税が課税されないという特例があります。この特例を受けるためには、申告が必要です。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、親族が相続した宅地について、一定の要件を満たす場合に、その評価額を最大80%減額することで、相続税の負担を軽減する制度です。主要な要件には、居住用や事業用の宅地であることなどが含まれます。特例の適用を受けるには申告が必要となります。
寄付を行った場合
相続財産を国や地方公共団体などに寄付した場合、その寄付額に応じて相続税が軽減されます。上記と同様に申告が必要になります。
相続税申告が必要かどうか微妙なケース
相続税の基礎控除を若干下回る場合、自身で計算を行い申告しないという選択は危険です。財産として計上すべきものが抜けている場合や、財産の評価方法が相続税のルールに従っていない場合が考えられます。適切な財産評価や必要な財産の計上ができていないと、後に追徴課税が発生するリスクがあります。
どういった財産が計上する必要があるのかについては、次の項目を確認してください。
相続税申告の注意点
財産として計上すべきものの範囲
相続税は、遺産総額 > 基礎控除の額を上回ればかかってきますが、
この遺産総額を正確に算出するために、どのような財産が相続財産になるか正確に把握することが非常に重要です。
遺産に含まれるもの
金融資産: 現金、預金、有価証券、小切手、国債など
不動産: 土地、建物、マンションなど
不動産上の権利:借地権、地上権、定期借家権
動産: 車、美術品、家財道具、貴金属など
債権: 貸付金など
相続財産によく足し漏れてしまう財産・債務
みなし相続財産
生命保険金、退職金はみなし相続財産と言われ相続財産ではないですが、
亡くなった方の死亡をきっかけとして受け取る財産として相続税の計算に含めなくてはいけません。
相続発生前3年以内の贈与 ※改正あり
もし、贈与を受けた日から3年以内に贈与者が亡くなってしまった場合、その贈与は「なかったもの」とみなされます。つまり、その贈与は相続財産に含まれ、相続税の課税対象となります。これを「生前贈与加算」といいます。
注意: 令和5年度の税制改正により、生前贈与が相続財産に加算される期間が、贈与者の死亡前3年間から7年間に延長されることが決まりました。この変更は、令和6年(2024年)1月1日以降に行われた贈与から適用されます。
マイナスの財産
マイナス相続財産とは、亡くなった人(被相続人)が残した相続財産のうち、借金や未払金などの価値がマイナスになる財産を指します。消極財産とも呼ばれます。
相続税を計算する際は、遺産の総額からマイナスの財産を差し引くことができます。これを「債務控除」といいます。具体的な例としては以下のようなものが該当します。
例
借入金(住宅ローン、車のローン、クレジット残債務など)
未払金(水道光熱費、通信費、医療費など)
敷金・保証金・預り金
公租公課(所得税、消費税、住民税、固定資産税 など)
申告期限
相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内です。この期限までに、申告書を作成し、被相続人の住所地を所轄する税務署に申告書を提出しなくてはいけません。 相続人の住所地を所轄する税務署ではないため、注意が必要です。
例
被相続人が2024年5月3日に亡くなった場合、申告期限は2025年3月3日になります。
申告期限が土日祝日にあたる場合は、翌日が期限となります。
相続税の納税も、上記の申告期限までに行うことになっています。申告期限までに納税をおこなわないと延滞税などのペナルティが発生する可能性があります。
相続人の範囲
相続税の基礎控除は3000万円⁺600万円×法定相続人の数で決まっていきます。
そのため、相続人の人数によって基礎控除の額が変わっていきます。相続人の数を数え前違えをしまうと基礎控除の額を間違えてしまうため、相続人の数を間違えずに数えることが必要になります。
相続人は大きく分けて、以下の2つに分類されます。
1. 配偶者
必ず相続人になります。
婚姻関係であることが要件となっていきます。
結婚してからの期間は加味されません。事実婚は相続の権利がありません。
2.血族
被相続人の血縁関係にある人です。
相続順位があります。
相続順位は以下の通りです。
第一順位 直系卑属: 子、孫など、被相続人から見て子孫にあたる人
第二順位 直系尊属: 親、祖父母など、被相続人から見て父母、祖父母にあたる人
第三順位 兄弟姉妹: 被相続人の兄弟姉妹
相続順位が同じ場合は、全員が相続人になります。
相続人の範囲を具体的に見てみましょう。
例
被相続人に配偶者と子がいる場合: 配偶者と子が相続人になります。
被相続人に配偶者と親しかいない場合: 配偶者と親が相続人になります。
被相続人に子がいない場合: 配偶者と親が相続人になります。親がすでに亡くなっている場合には、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹もなくなっている場合には、その子供に引き継がれます。これを代襲といいます。
特に、実務では代襲が見落とされやすいため注意が必要です。
兄弟姉妹の代襲は1回までです。再代襲はありません。
被相続人に配偶者も血族もいない場合: 相続人はいません。
よくある質問
Q 生命保険金は相続財産に含まれる?
A 結論から言ってしまうとみなし相続財産として相続財産に含まれます。
生命保険金を相続財産として計上するにあたって、注意点があります。
生命保険金であれば、法定相続人の数×500万円まで非課税が設けられています。
例
保険金 2000万円
相続人 配偶者 子供 2人 合計 3人 子供のうち1人が放棄をしている場合
500万円×3人(放棄をしていても法定相続人の数としてカウントします)
=1500万円
相続税の課税対象 2000万円(保険金) - 1500万円(生命保険金の非課税) = 500万円
補足:なぜみなし相続財産と言われるのか?
通常、生命保険金は相続財産ではなく、保険契約に基づき受取人が受け取るものであるため、受取人固有の財産として考えられているためです。
よって、生命保険金が遺産分割の対象とならず、原則として遺産分割協議書への記載は不要ということになります。
Q 配偶者が全財産を取得して、特例を使って相続税が0円になりました。申告は必要ですか?
A 特例をつかう場合には、申告が必要になります。
Q 申告は自分でできる?
A 財産が預金のみで相続人が1人の場合、相続税申告書を自分で作成してみてもいいかもしれません。
しかし、それ以外のケースでは、税理士への依頼を強くおすすめします。
なぜなら、相続税は非常に複雑な税法であり、申告期限が厳守されるため、専門家のサポートが必要不可欠だからです。
特に、以下の場合は税理士への相談がより重要となります。
・相続財産が不動産や株式など、評価が難しい財産を含む場合
・相続人が複数いる場合
税理士に依頼することで、
・正確な申告書の作成
・節税対策
・税務調査への対応
といったメリットが期待できます。
相続は人生において大きな出来事であり、税務に関するトラブルを避けるためにも、専門家のサポートを受けることを検討しましょう。
まとめ:相続税申告は専門家に相談しよう
相続税申告は、遺産が基礎控除額を超える場合や、特例を受ける場合などに必要です。しかし、微妙なラインで判断に迷うことも。財産の評価や申告期限など、注意点も多いため、一人で判断せず、税理士に相談することをおすすめします。