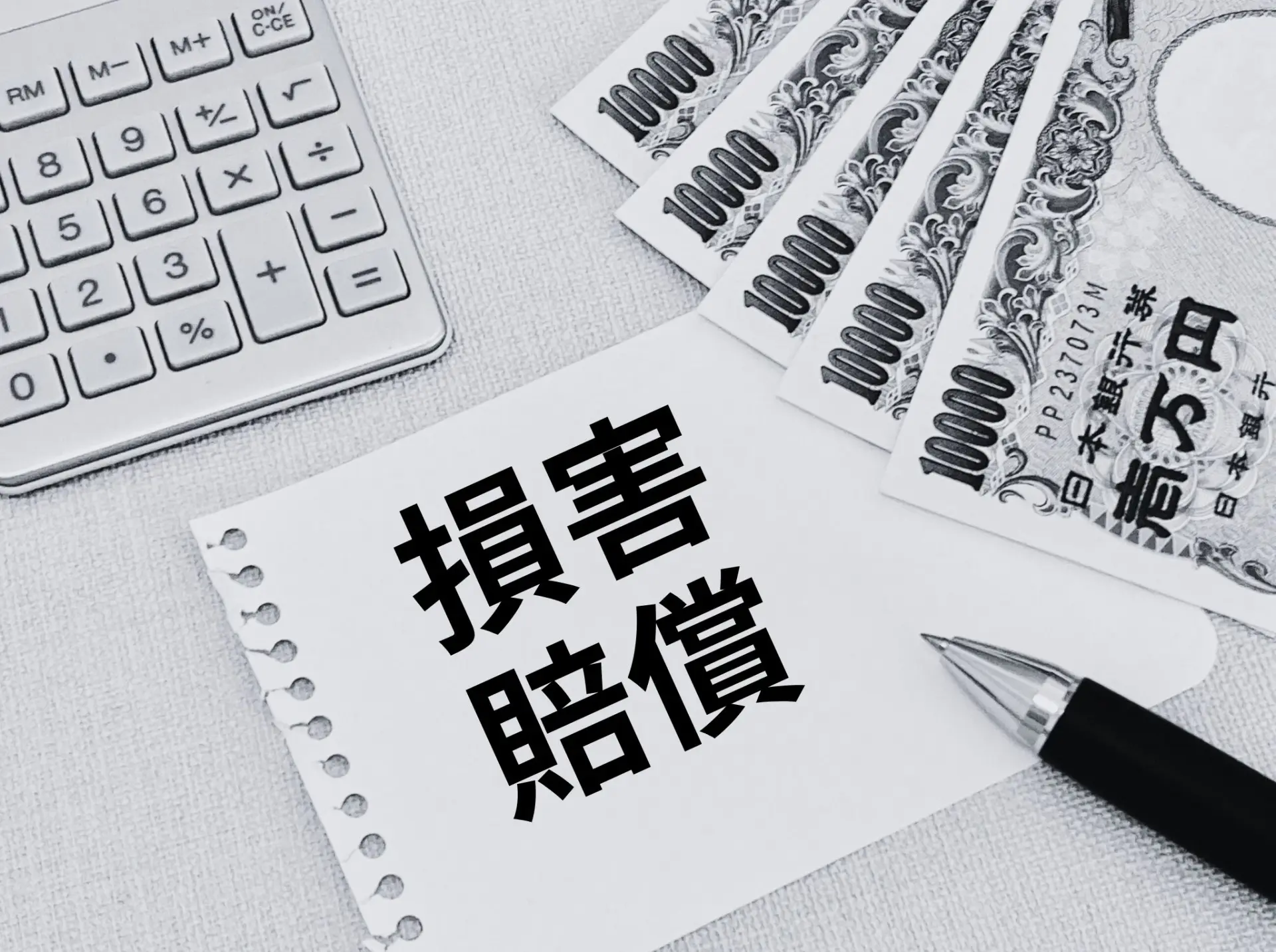親などの相続が発生すると相続人はすべての財産を引き継ぐ権利を有します。負債を負ったまま亡くなるケースもありますが、損害賠償責任を負ったまま亡くなった場合、相続人は放棄をすることができるのでしょうか。当記事では相続人の責任や義務を負ってしまった場合の対処法について解説します。
損害賠償責任は相続人に支払う義務がある
損害賠償責任は
相続人に支払う義務がある
被相続人が債務を負っていた場合、相続人に支払う義務が承継されます。被相続人に損害賠償責任がある場合も同じで被相続人が損害賠償責任を負ったまま亡くなった際は、相続人に賠償義務が承継され、請求されることになります。
損害賠償責任が被相続人が亡くなった後に確定した場合も財産を承継する者に義務が生じます。例えば、交通事故を起こした時に加害者である被相続人が亡くなっているケースなどが考えられるでしょう。スピード違反などによる交通事故で他人に被害を与えた場合は被害者に損害賠償を行う必要がありますが、自動車による事故と同時に死亡してしまう可能性もあります。被害者が事故により怪我をさせてしまった場合や身体障害が残ったケースなどでは家族が被害者への賠償責任を負う流れとなります。
損害賠償責任は放棄可能
被相続人が他人に対して負っている損害賠償責任や慰謝料は相続放棄をすることが可能です。ただし損害賠償責任や借金などの債務だけを放棄することはできません。そのため、相続放棄の手続きを行うと固有の財産である生命保険は受け取ることができますが、被相続人名義の自宅の土地・建物などの不動産や預貯金、株式などすべての相続財産を承継する権利を失います。相続放棄はそれぞれの判断で家庭裁判所にて行うことが可能です。相続放棄の期限は相続発生から原則3ヶ月以内に書類の提出まで完了することが必要となります。期限を過ぎるか財産の処分を行うと単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなりますので、期限には十分に注意をしましょう。
相続の対象となる財産がしっかりと調査できておらず、期限内にプラスの財産とマイナスの財産がどちらが大きいか確認できない場合は限定承認という方法を取ることも可能です。限定承認は単独でできる相続放棄とは違い、相続人全員で行う必要がありますが、引き継いだ財産の範囲で債務や損害賠償について責任を負うという方法です。限定承認を行うことで多額の債務を負うことになる状況を回避することができます。
相続放棄をする場合の注意点
相続放棄をすることで、相続権を失いその人は遺産相続に参加することがなくなりますが、結果として兄弟姉妹や甥・姪など他の相続人や次の順位の親族のそれぞれの負担が大きくなるリスクがあります。このような場合は戸籍を確認し、他の相続人に事前に連絡して相続放棄の手続きを行うようにしましょう。相続放棄をすることで自分が債務を免れることによって他の相続人に負担が大きくなってしまうことでトラブルになる事例が多くあります。他の相続人も相続放棄について検討ができるように、早めに連絡するようにしましょう。
また、相続放棄を行い、家庭裁判所に受理されると後で取り下げることはできません。財産の額を調査してからじゃないと、プラスの財産の額と債務や損害賠償の額がどちらか大きいかわからないので、財産をまとめた一覧を作成し、どちらを選択するのがメリットがあるのかよく検討してから選択するようにしましょう。
相続放棄ができないケース
損害賠償を負っているケースで相続放棄ができないケースもあります。相続放棄ができないケースとは相続人自身に責任があるケースです。有名な裁判例としては認知症で意思能力が弱っている親が事故を起こして、相続人自身が損害賠償責任を問われたケースです。この事例は相続人自身が被相続人である親を介護する立場であったにもかかわらず、十分な注意を怠って事故を起こしてしまったため、被相続人の債務とはならず相続放棄により損害賠償責任を免れることができなかったという事例です。他にも未成年者を監督する立場であるにもかかわらず怠ったケースなどが考えられます。
このようなケースでは、相続人自体に責任があるため、相続放棄ができず支払いに応じる必要があります。
不明点は専門家に相談を
相続に関連するお悩みや不安がある場合は知識と経験が豊富な弁護士や司法書士、税理士等の専門家にサポートを依頼するようにしましょう。相続に関する問題はさまざまで多くの事例を経験しないと解決できないことが多くあります。
相続が発生し、遺産を承継する際は民法や相続税法などさまざまな法律が複雑に絡み合うため、自身で解決することが難しいケースも多くあるでしょう。専門家に依頼することで費用は掛かりますが、安心して対応を行うことができます。
また、遺言書を書くなど生前に対策をしておくことで遺産分割のために相続人全員で話し合う必要がなくなるなど負担を減らすことができます。また、生前贈与などで節税策についても検討することができるでしょう。事前の対策についても遺言の内容や書き方などを専門家に相談することでより有効な対策となります。初回の相談は無料で対応してくれる法律事務所や税理士事務所も多いので、まずは電話やメールなどで気軽に相談してみるとよいでしょう。