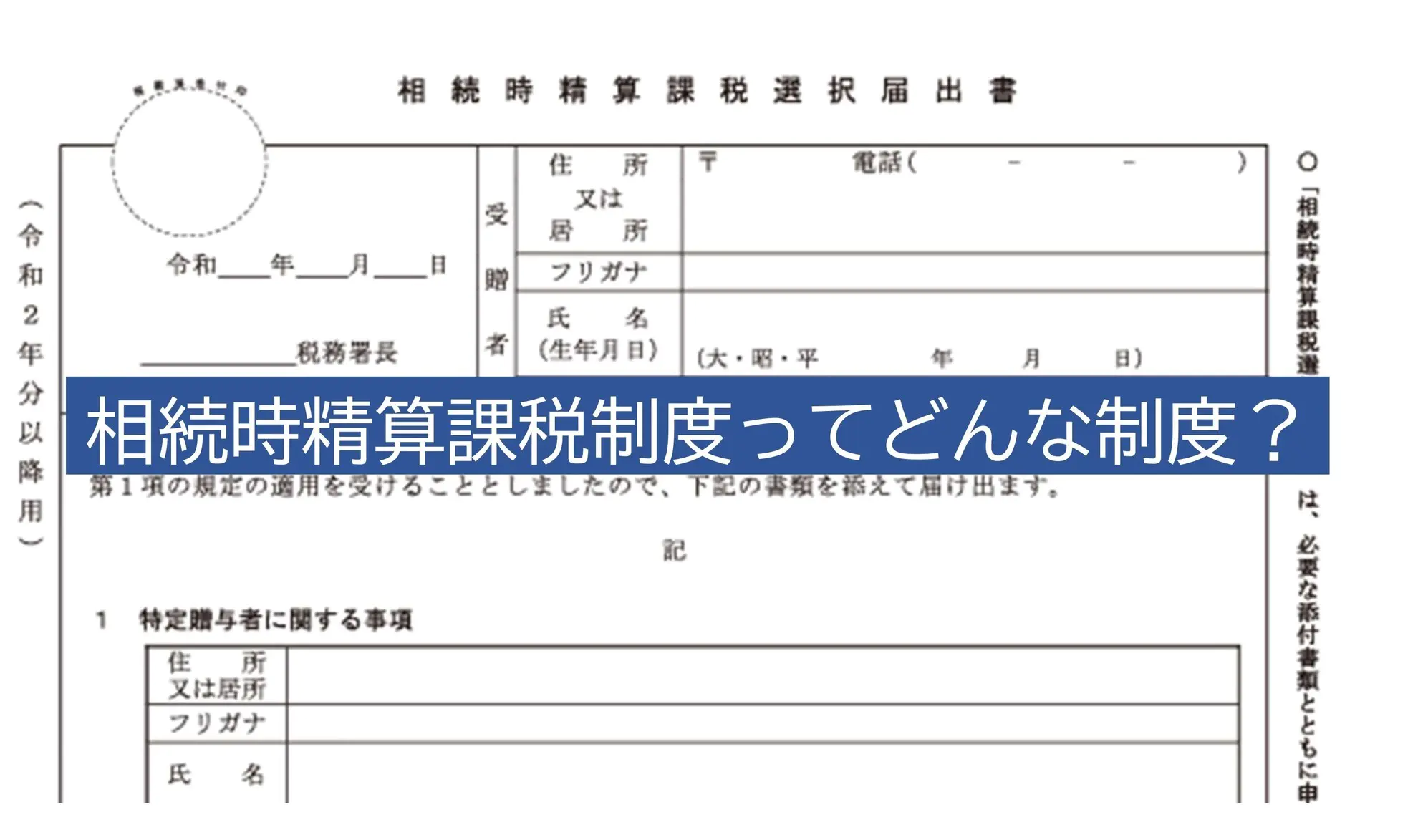相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の贈与者(祖父母・父母など)から18歳以上の受贈者(孫・子など)に対して財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
この制度を使うには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に戸籍等の一定の書類を添付した相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。
この制度を利用すれば、合計で2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった際に、贈与財産と相続財産を合算した上で相続税を計算し、一括で納税する仕組みです。
なお、一度精算課税制度を選んでしまうと戻ることが出来ないので注意が必要です。
2024年の改正があるまでは、税金を繰り延べるだけの制度でしたが、改正により毎年110万円の非課税枠ができて、利便性が格段に向上しました。
相続時精算課税制度の110万円の枠は、暦年課税制度の110万円の枠と違い、相続が発生したとしても、相続財産に足されることはありません。
そのため、毎年110万円以下の贈与を行う方には、暦年課税を使うよりも精算課税制度を使った方が、節税が出来るということになります。
精算課税制度を選ぶべき人 暦年課税制度を選ぶべき人
精算課税制度を選ぶべき人
①相続税がかからない、または少額な人
相続財産が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人)以下で、そもそも相続税がかからない、または少額な場合、精算課税を選択することで、生前に毎年110万円まで非課税で贈与できるというメリットがあります。
②7年以上長生きしないと思っている人
毎年コツコツ贈与を行った場合、暦年課税を適用した場合の相続時の控除額は最大で100万円です。一方で相続時精算課税制度を選択した場合は110万円×7年間で最大770万円まで控除を受けることが可能です。
③短期間に多額の財産を贈与したい人
相続発生前に、多額の財産を短期間に贈与したい場合に有効です。
暦年課税では、年間110万円の非課税枠しかありませんが、精算課税であれば、2,500万円まで非課税で贈与することができます。また、精算課税制度を2500万円の枠を超えたとしても一律20%の贈与税しか課税されないため、暦年課税(最大55%)よりも少ない税金で資産を移動させることができます。
暦年課税制度を選ぶべき人
①7年超の長期間にわたって、110万円の基礎控除を超える贈与をおこなう人
毎年10年間孫に対して200万円贈与を行った場合、合計で2,000万円(200万円×10)の財産を移すことができ、トータルで支払う贈与税も適用税率が10%のため、90万円で済みます。
仮に相続税が40%の方の場合だと、800万円(2,000万円×40%)の相続税が抑えられます。支払った贈与税を加味すると710万円(800万円-90万円)節税できたこととなります。
計画的に贈与を行うことで、節税に大きく寄与することとなります。
一方で、相続人に対して、贈与を行うと7年以内の贈与は相続財産として扱われてしまうため、注意が必要です。
精算課税制度の注意点
メリットがたくさんある一方で注意すべき点もたくさんあります。
①一度選んだら戻れないこと
精算課税制度を一回選択すると暦年課税制度に戻ることが出来ません。適用にあたって慎重に検討しましょう。
②課税庁にとって有利な制度であること
精算課税制度を選択した場合に、選択したときから相続が発生するときまでの全ての期間が加算対象となります。そのため、課税庁は申告の有無にかかわらず、相続時に加算することが出来てしまいます。そういった意味で時効が成立しなくなる制度といえます。
そのため、贈与契約書をしっかり結び、公証役場でしっかり確定日付をもらって証拠を残すことが大事です。
③申告期限を過ぎてしまうと2500万円の控除をうけることが出来ないこと
2,500万円の控除は申告期限(贈与をおこなった年の翌年2月1日から3月15日まで)に申告をした場合に限り適用されます。
うっかり申告を忘れてしまうと2500万円の控除が使えなくなってしまいます。
なお、適用しなかった控除額は翌年以降に繰り越されることとなります。
④父親母親ともに精算課税選択したら、110万円の控除でなくなること
改正により110万円の控除が設けられましたが、受贈者(財産をもらう人)1人に対して110万円の控除となっているため、注意が必要です。
そのため、父親母親ともに精算課税制度を選択した場合、220万円(110万円×2)の控除額ではなく、110万円となります。
110万円の按分方法はもらった財産の価額に応じて計算を行います。
なお、2500万円の控除は父親母親いずれに対して使うことができます。
まとめ
使い勝手が増した精算課税制度ですが、一回選んだら戻れないため、リスクをしっかり考えて判断する必要があります。
どちらが有利かは専門家に判断を仰ぐことをお勧めします。
最後までお読みいただきありがとうございます。