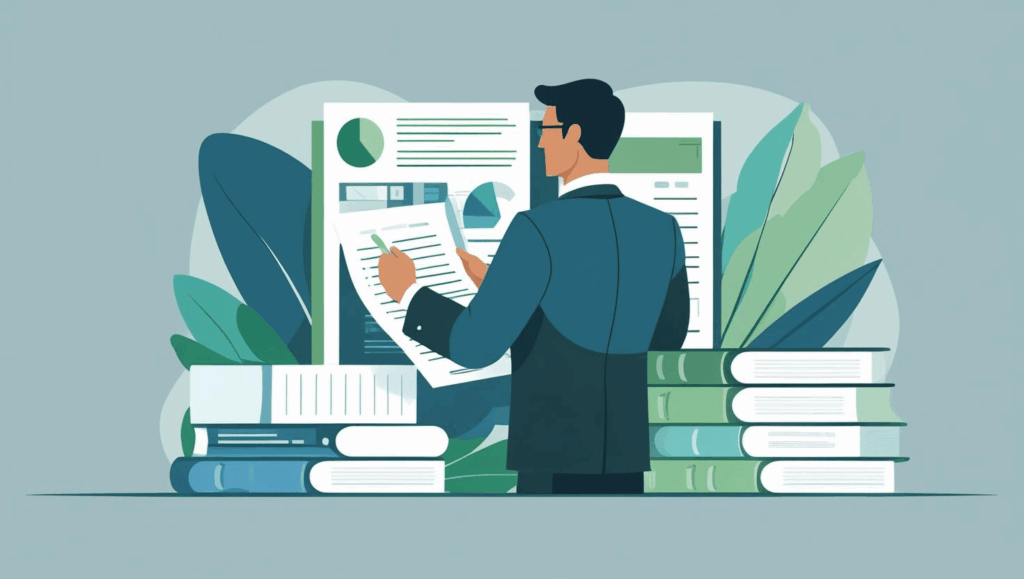
相続が発生し、相続税の申告・納税が完了して一息ついたのも束の間、税務署からの税務調査の連絡に不安を感じる方は少なくありません。国税庁の統計によると、相続税申告者のうち約5~20%が税務調査の対象となり、調査を受けたケースの80%以上で申告漏れが指摘され、追徴課税が発生しています。
この記事では、相続税の税務調査の基本知識から、税務署に目をつけられやすい人の特徴、そして税務調査を回避・対策するための具体的な方法まで、分かりやすく解説します。
1. 相続税の税務調査の基礎知識
税務調査とは、相続税の申告内容に間違いがないか、申告漏れや不正がないかを確認するために税務署が行う調査手続きです。納税の公平性を保つことを目的としています。
1-1. 税務調査の種類
税務調査には「任意調査」と「強制調査」の2種類があります。
- 任意調査: 事前に税務署から連絡が入り、調査日時を決めて行われることが一般的です。拒否することはできませんが、裁判所の令状は不要で、税務職員からの質問への回答や書類の確認が主な内容です。相続税に関する税務調査のほとんどが任意調査です。
- 強制調査: 脱税の隠蔽工作が悪質である場合や脱税額が1億円を超えるなど、重大な脱税が疑われる場合に、裁判所の令状に基づいて急遽実行されます。国税局査察部が担当し、拒否はできず、資料の押収なども行われます。
1-2. 税務調査の時期
税務調査は、相続税の申告書提出から1~2年後の8月~11月頃に行われることが多いです。これは、税務署の人事異動が毎年7月に行われるため、その後から調査が本格化するためとされています。3年目以降に行われることもありますが、年数が経つにつれて調査の確率は減少する傾向にあります。
1-3. 事前の銀行調査
税務署は税務調査を行う前に、法律の権限を使って故人やその親族名義の口座履歴を金融機関から開示させ、事前に調査しています。過去5年間分、場合によっては10年間分の通帳履歴を調べ、多額の入出金や頻繁な出入金、不審な動きがないかを確認します。この事前調査で怪しい点が見つかった場合にのみ、税務調査を実施するというのが、高い追徴課税率のカラクリです。
2. 税務調査の対象になりやすい人の特徴
税務署が税務調査の対象を選定する際には、特定のパターンに合致する人や状況に注目する傾向があります。以下に、税務署に目をつけられやすい人の主な特徴をまとめました。
2-1.相続財産が高額な場合
一般的に2億円以上を相続すると、税務調査の対象になりやすいと言われています。税理士法人とおやまでも3億円を超える相続財産の場合、税務調査される確率が一気に跳ね上がる感覚があります。これは、財産が大きくなると計算ミスや申告漏れの可能性が高まるため、追徴課税の可能性も大きいと税務署が判断するためです。
2-2.財産の動きに不審な点がある場合
- 相続財産に現金が多く、出入りが頻繁な場合は、相続税対策として財産を移転したと疑われる可能性があります。
- 亡くなる直前に口座から多額の現金を引き出しており、その使途が不明な場合。税務署は引き出された現金が家族に手渡されたり、自宅に隠されたりしている可能性を疑います。
- 多額の借入金があるのに、それに見合う相続財産がない場合も、財産隠しや申告漏れを疑われます。
2-3.名義預金や暦年贈与がある場合
- 税務署が特に力を入れて調査しているのが、名義預金や暦年贈与です。名義預金とは、口座名義人と実際にお金を出した人が違う預金のことで、被相続人が通帳や印鑑を管理していたり、名義人自身が自由にお金を動かせない場合、被相続人の財産とみなされます。
- 収入の少ない専業主婦や学生の口座に多額の預貯金がある場合、名義預金や生前贈与を疑われる可能性が高いです。
- 暦年贈与(年間110万円以下の非課税贈与)を規則正しく繰り返している場合、「最初から多額の贈与をするつもりだった」として、定期贈与とみなされ一括贈与として贈与税を求められることもあります。
2-4.被相続人の生前の状況と申告内容の不一致
- 毎年高額の所得税を納めていたにもかかわらず、相続税の申告書にあまり財産が残っていない場合。税務署は所得税の確定申告や年末調整で故人の収入を把握しており、その収入と相続財産のバランスを見比べます。
- 上場企業の社長や重役、医師、弁護士など、社会的地位が高く高収入が予想される職業の故人の場合、税務署のチェックが厳しくなる傾向があります。
2-5.海外資産がある場合
- 相続財産に海外資産が含まれる場合も、税務調査の可能性が高まります。
- 海外への1回あたり100万円を超える送金や入金は金融機関から税務署に情報が共有されるため、申告内容との差異があれば調査対象となりやすいです。
2-6.申告内容自体に問題がある場合
- 税理士に依頼せずに自分で相続税を申告した場合、計算ミスや財産の見落とし、特例の適用誤り、添付書類の不足などの不備が発生しやすいため、税務調査の対象になりやすいです。
- 相続税の申告が必要なのに申告していない(無申告)場合。基礎控除や配偶者控除などを誤って適用し、本来なら申告が必要だったケースや、財産の見落としで無申告になったケースなどが指摘されます。死亡届が提出されると税務署にも情報が伝わるため、無申告を隠し通すことはできません。
- 親族間で揉めており、複数の相続人から内容の異なる申告書が提出されている場合も、疑われやすい傾向にあります。
2-7.税務署に外部からの情報がある場合
- 法定調書(不動産や株式の取引、生命保険金、海外送金などの情報)によって、高額な財産の購入・売却、海外送金などはすべて税務署に筒抜けになっています。
- 投書(投げ):一般からの投書によって、具体的な不正や脱税の内容が詳しく書かれている場合、税務署はほぼ確実に税務調査を行います。
3. 税務調査を回避・対策するための方法
税務調査は100%回避できるものではありませんが、適切な対策を講じることで、その確率を大幅に低減させることが可能です。また、万が一調査が入ってもスムーズに対応できるよう準備しておくことが重要です。
3-1.相続税を正しく申告する
大前提として、すべての相続財産を見落としなく調査・把握し、計算ミスがないように複数回確認して正確に申告することが最も重要です。
3-2.被相続人の財産を正確に把握する
生前から家族で資産の状況を共有し、財産目録などを作成しておくことで、申告漏れのリスクを減らせます。
3-3.相続・贈与に関するやり取りは記録として残す
- 生前贈与を行う場合は、贈与契約書を作成し、現金の手渡しではなく銀行振込を利用するなど、証拠を残すことが重要です。
- 遺産分割協議書を必ず作成し、誰がどの遺産を相続するかを明確に記録しておきましょう。
3-4.相続税に強い税理士に依頼する
- 税理士に申告書作成を依頼すると、申告内容の信頼性が高まり、税務調査の対象になる確率が低くなります。税理士の署名があることで、税務署からの信頼度は大きく向上します。
- 特に「書面添付制度」を利用すれば、税務署は税理士に内容の確認を行うことで、税務調査を省略するケースもあります。
- 万が一税務調査が入った場合でも、相続税に強い税理士が相続人の代理として税務署対応を行うため、安心して調査に臨むことができます。
- 税務調査に強い税理士の探し方
- 専門分野を確認する: 税理士にも専門分野があります。相続を得意としている税理士か、ウェブサイトなどで確認しましょう。
- 依頼前に面談する: 信頼関係が重要なので、事前に面談して人柄やコミュニケーション能力も確認することをお勧めします。
- 実績を確認する: 相続税申告や税務調査の経験が豊富な税理士を選びましょう。実績のある税理士は、適切な事前対策や当日対応のアドバイスをしてくれます。
4. もし税務調査が入ってしまったら?:対応の準備と流れ
税務署からの連絡があった場合でも、焦らず適切に対応することが大切です。
4-1. 必要な準備と書類
- 申告書の内容を再確認する: 申告内容に間違いや見落としがないか、あらためて確認し、計算ミスがないか検算しましょう。
- 財産の洗い直しをする: 見落としている預貯金、不動産、有価証券、現金(タンス預金など)がないか、自宅や金庫をよく探しましょう。特に、亡くなる前3年以内に生前贈与された財産は相続財産として申告が必要です。
- 申告内容を証明する資料を揃える: 申告時に使用した資料の原本、故人や相続人全員の預貯金通帳、不動産の権利証などを準備しておくと心強いです。
- 税理士に依頼する: 自分で申告した場合でも、この時点で相続税に強い税理士に依頼し、申告内容の確認と税務調査の立ち会いを依頼できます。
4-2. 調査の流れと注意点
- 調査開始 (午前): 午前10時頃に税務職員2名(質問係と記録係)が訪問し、聞き取り調査が行われます。故人の家族関係、居住歴、趣味、仕事、生活費、そして相続人に関する情報などが質問されます。嘘をつく必要はありませんが、聞かれたことのみを簡潔に回答し、余計な発言は控えましょう。
- 昼休憩: 12時頃に昼休憩となり、調査官は外で食事をとるため、相続人が食事を用意する必要はありません。
- 調査再開 (午後): 午後からは、預金通帳などの現物確認や、金庫、印鑑、貴重品の保管場所などの確認が行われます。求められた部屋や金庫の開示を拒否すると心証が悪くなる可能性があるため、協力することが推奨されます。
- 調査終了: 午後5時頃に調査が終了することが多いですが、内容によっては2日間にわたることもあります。調査官は質問と回答を書面にまとめるので、内容を確認し、税理士にも確認してもらった上で署名押印しましょう。
5. 申告漏れがあった場合のペナルティ
税務調査の結果、申告漏れなどの誤りが指摘された場合、本来納めるべき相続税に追加して、以下の加算税や延滞税が課せられます。
- 延滞税: 納税を期限内に行わなかったことに対する利息的な税金です。
- 加算税
- 過少申告加算税: 申告はしたが、本来の税額より少なかった場合に課せられ、追加税額の10~15%が加算されます。
- 無申告加算税: 申告が必要なのに期限内に申告しなかった場合に課せられ、追加税額の15~20%(令和6年以降は最高30%)が加算されます。
- 重加算税: 故意に財産を隠したり偽装したりして、相続税を少なく申告した場合に課せられ、無申告の場合は40%、過少申告の場合は35%と最も重いペナルティです。
- 刑事罰: 悪質な脱税と判断された場合、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科される可能性があります。
6.まとめ
相続税の税務調査は、多くの方にとって大きな不安の種です。特に、相続財産が高額な方、現金・預金の動きに不明瞭な点がある方、ご自身で申告された方は、調査対象に選ばれやすい傾向があります。
しかし、必要以上に恐れることはありません。相続財産を正確に把握し、適切な申告を行うこと、そして何より相続に強い税理士を味方につけることが、最大のリスク対策となります。万が一、税務調査の連絡があった際も、私たちが専門家として立ち会い、皆様をしっかりとサポートいたします。
相続に関するご不安やお悩みは、どんな些細なことでも構いません。相続税のプロフェッショナルである税理士法人とおやまへ、まずはお気軽にご相談ください。

