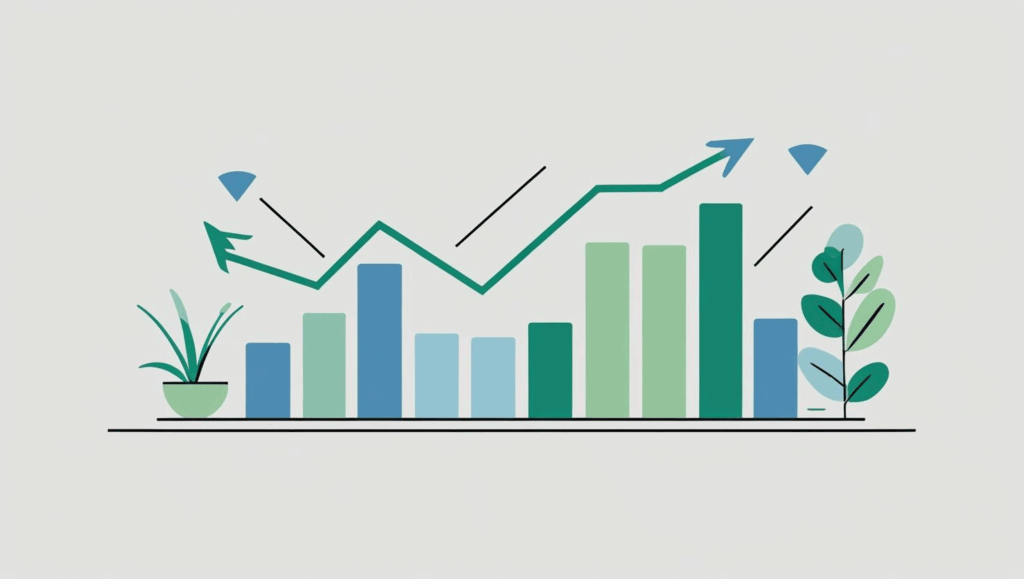
「親が亡くなり、遺産の中に株式が見つかったけれど、どうやって価値を計算すればいいのだろう?」 「相続税の申告が必要だけど、株の評価方法が複雑でよく分からない…」
このようにお悩みではないでしょうか。
故人の大切な財産である「株式」を相続した場合、その価値を正確に評価し、適切に相続税を申告・納税する義務があります。株式の評価は、証券取引所で誰もが売買できる「上場株式」か、それ以外の「非上場株式」かによって、その計算方法が全く異なります。
この記事では、相続税務に精通した税理士の視点から、上場株式・非上場株式それぞれの相続税評価額の計算方法、ご自身での調べ方、そして節税やトラブル回避のために知っておくべき注意点まで、網羅的に解説します。
この記事を最後まで読めば、株式の相続に関する一連の流れと、あなたが今すべきことが明確になるはずです。
1.上場株式の相続税評価額|4つの株価から最安値を選ぶのが基本
上場株式とは、東京証券取引所などの金融商品取引所に上場されている株式のことです。日々株価が公開されているため、比較的ご自身でも評価額を計算しやすいのが特徴です。
1-1. 評価額の計算方法:相続人に最も有利な価格を選択できる
上場株式の株価は常に変動しているため、相続税を計算する際は、相続人にとって最も有利な(=最も低い)価額を選べるように、以下の4つの価格を比較します。
<比較する4つの株価>
- 課税時期の終値:相続開始日(通常は被相続人の死亡日)の最終的な株価。
- 課税時期が属する「月」の終値の月間平均額:例:相続日が4月20日なら、4月中の毎日の終値の平均額。
- 課税時期が属する「前月」の終値の月間平均額:例:相続日が4月20日なら、3月中の毎日の終値の平均額。
- 課税時期が属する「前々月」の終値の月間平均額:例:相続日が4月20日なら、2月中の毎日の終値の平均額。
この4つのうち、最も低い価格をその株式の1株あたりの評価額として採用します。
相続税評価額の計算式はシンプルです。 相続税評価額 = 1株あたりの評価額(上記4つのうち最も低い価格) × 保有株式数
【具体例】 相続開始日が4月20日、保有株式が2,000株で、各時点の株価が以下の場合
① 4月20日の終値:5,000円
② 4月の終値の月間平均額:4,700円
③ 3月の終値の月間平均額:5,100円
④ 2月の終値の月間平均額:4,900円
この中で最も低い株価は②の4,700円です。 したがって、相続税評価額は 4,700円 × 2,000株 = 940万円 となります。
1-2. 株価の具体的な調べ方【残高証明書・ネット】
4つの株価は、以下の方法で調べることができます。
- 証券会社の「残高証明書」を利用する
被相続人が口座を開設していた証券会社に連絡し、「相続開始日時点」の残高証明書を請求します。これが最も確実な方法です。証券会社によっては、依頼すれば過去3ヶ月分の月間平均額が記載された参考資料も一緒にもらえる場合があります。
- インターネットを利用する
① 相続開始日の終値: 「Yahoo!ファイナンス」などの金融情報サイトで、銘柄名や銘柄コードを検索し、「時系列」データから該当日付の終値を確認できます。
②~④ 月間平均額: 「日本取引所グループ」の公式サイト内、「マーケット情報」→「統計情報(株式関連)」→「月間相場表」から、各月の終値平均額を調べることが可能です。
一見シンプルに見える上場株式の評価ですが、以下のようなケースでは特別な対応が必要となり、申告漏れや評価誤りを起こしやすいので注意が必要です。
1-3. 見落とし厳禁!上場株式の評価における7つの注意点
1-3-1.相続開始日が土日祝日だった場合
証券取引所が休場のため、その日の終値は存在しません。この場合は、相続開始日に最も近い日の終値を採用します。連休などで最も近い日が複数ある場合は、それらの日の終値の平均額を使用します。
1-3-2.権利落ち・配当落ち日をまたぐ場合
配当金などを受け取る権利が確定する「権利確定日」の前後では、株価が一時的に下落(権利落ち・配当落ち)します。この一時的な下落を利用した評価を防ぐため、相続開始日が権利落ち日から基準日までの間にある場合は、権利落ち日の前日の終値を評価に用いるという特別なルールがあります。
1-3-3.端株(単元未満株)の申告漏れ
通常の取引単位(例:100株)に満たない「端株」は、証券会社の残高証明書に記載されないことがあります。配当金の通知書に記載されている「所有株式数」を確認したり、信託銀行などの株主名簿管理人に問い合わせたりして、申告から漏れないようにしましょう。
1-3-4.配当期待権・未収配当金も相続財産
受け取る権利が確定しているものの、まだ入金されていない配当金も相続財産です。
- 配当期待権:配当基準日の翌日から配当確定日までの間に死亡した場合の、未収の配当金。評価額は「予想配当金額 × (1 – 源泉徴収税率20.135%) × 保有株式数」で計算します。
- 未収配当金:配当確定日の翌日以降に死亡した場合の、未収の配当金。
1-3-5.重複上場株式の有利選択
東京、名古屋など複数の証券取引所に上場している株式の場合、各市場の株価を比較し、最も低い価格がつく市場の株価を選択して評価することができます。
1-3-6.TOB(株式公開買付)対象銘柄だった場合
被相続人がTOB対象銘柄を保有していた場合、相続開始前か後かによって評価上の注意点が異なります。TOBに応じていない場合や上場廃止となった場合は、特定口座での譲渡ではないため確定申告が必須となり、他の上場株式との損益通算や譲渡損失の繰越控除の適用ができないことがあります。
1-3-7.売却済み・未受渡しの株式
相続開始直前に株式を売却していても、代金の受渡しが完了していない(通常、約定日から3営業日後)場合があります。この場合、残高証明書に株式が記載されていても、評価対象は株式ではなく、売却代金から手数料を引いた「未収入金」として計上します。
2. 非上場株式の相続税評価額|専門知識が必須の複雑な領域
非上場株式とは、証券取引所に上場していない株式で、主に中小企業のオーナー経営者やその親族が保有しています。市場価格がないため、その評価は非常に複雑で、専門的な知識が不可欠です。
評価方法は、会社の規模(大会社・中会社・小会社)や、相続する人が経営権を握る「同族株主」か、それ以外の少数株主かによって、以下の3つの方式を組み合わせて用います。
| 評価方式 | 概要 | 特徴 |
| 類似業種比準方式 | 事業内容が似ている上場企業の株価を基に、配当・利益・純資産を比較して評価する方式。 | 比較的、評価額が低くなる傾向がある。 |
| 純資産価額方式 | 会社の総資産を相続税評価額で再評価し、そこから負債を差し引いた純資産額を基に評価する方式。 | 会社の資産(特に不動産)の時価が高い場合、評価額も高額になりやすい。 |
| 配当還元方式 | その株式を保有することで得られる年間の配当金額を基に評価する方式。 | 同族株主以外の少数株主が株式を取得した場合にのみ適用。評価額は3つの方式の中で最も低くなる傾向。 |
これらのどの方式を、どの割合で用いるかは、国税庁の複雑なルールに基づいて決定されます。特に、会社が保有する土地や建物の評価も必要になるため、ご自身で正確な評価額を算出するのは極めて困難です。
非上場株式の評価は、必ず相続に強い税理士に依頼してください。
3. 株式を相続する際の共通の重要手続きと注意点
株式の種類にかかわらず、相続に際しては以下の手続きや注意点も押さえておきましょう。
3-1.被相続人の準確定申告
故人が生前に株式の売却益や配当所得を得ていた場合、相続人は亡くなったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、故人の所得税の申告・納税(準確定申告)を行う必要があります。
3-2.遺産分割協議
遺言書がない場合、株式は相続人全員の共有財産となります。誰がどの株式を相続するのか、遺産分割協議で決定しなければなりません。株式は現金と違って分けにくく、評価額を巡ってトラブルになることもあるため、慎重な話し合いが必要です。
3-3.名義変更(名義書換)
相続した株式を売却したり、配当金を受け取ったりするためには、必ず被相続人から相続人の名義に変更する手続きが必要です。上場株式は証券会社へ、非上場株式は株式の発行会社へ連絡して手続きを進めます。
3-4.売却時の譲渡所得税
相続した株式を売却して利益(譲渡所得)が出た場合は、確定申告をして税金を納める必要があります。
- 譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 売却手数料)
- 税率 = 20.315% (所得税15% + 復興特別所得税0.315% + 住民税5%)
3-5.相続税対策における不動産との比較
一般的に、相続税の評価額を引き下げる効果は、株式よりも不動産の方が高い傾向があります。土地や建物は時価よりも低い路線価や固定資産税評価額で評価される上、「小規模宅地等の特例」などが適用できれば、評価額を最大80%も減額できる可能性があるためです。
4. 株式の相続でお悩みなら「税理士法人とおやま」へご相談ください
「自分の場合はどうなるんだろう?」 「非上場株式の評価や手続きを、まるごとお願いしたい」 「まずは話だけでも聞いてみたい」
このようにお考えでしたら、ぜひ私たち「税理士法人とおやま」の初回無料相談をご利用ください。当法人は、相続税申告に特化しており、これまで数多くの株式を含む相続案件を手掛けてまいりました。特に、評価が複雑で税理士によって評価額に大きな差が出やすい非上場株式の評価には豊富な実績とノウハウがございます。
税理士法人とおやまが選ばれる理由
- 相続税に特化した圧倒的な実績:私たちは相続税申告に特化しているからこそ、非上場株式の評価、土地評価、特例の適用など、あらゆる論点を駆使して適正な評価額を算出し、円滑な申告を実現できます。
- 初回無料相談:まずはご家族の状況や財産内容をじっくりお伺いし、今後の流れや必要な手続き、お見積りを分かりやすくご説明します。相談したからといって無理に契約を迫ることは一切ございませんので、ご安心ください。
- ワンストップのサポート体制:相続税申告だけでなく、不動産の名義変更(相続登記)や遺産分割協議書の作成など、提携する司法書士と共にワンストップでサポート。お客様の手間を最小限に抑えます。
- お客様に寄り添う姿勢:私たちは、ただ税金を計算するだけの専門家ではありません。ご家族が円満に相続を乗り越え、新たなスタートを切れるよう、親身に寄り添い、最善のご提案をいたします。
相続は、誰にとっても初めての経験で、不安なことばかりだと思います。その不安を解消し、納得のいく形で手続きを終えるために、私たち専門家が全力でサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせいただき、あなたの状況をお聞かせください。
この記事の監修税理士

税理士法人とおやま
税理士 遠山 大地
東京・高田馬場で、相続税申告と相続対策に特化した税理士をしております。これまで300件以上の相続税申告に携わってまいりました。豊富な経験と専門知識を活かし、お客様の大切な財産を次世代へ円滑に引き継ぐお手伝いをいたします。
相続は、人生において大きな節目となる出来事です。相続税の手続きは複雑で専門的な知識が求められるため、多くの方が不安を抱えていらっしゃいます。
お客様一人ひとりの状況に寄り添い、分かりやすく丁寧なご説明を心がけておりますので、相続に関するお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

