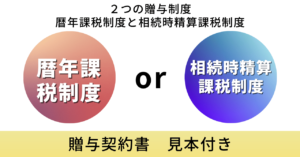「名義財産」という言葉をご存じでしょうか。
これは、被相続人(亡くなった方)がお金を出して、孫や相続人名義の預金通帳や保険契約をすることを指します。
具体的には「名義預金」や「名義保険」と呼ばれます。
一見すると相続税対策になりそうな名義預金ですが、実は税務署から「真の所有者は被相続人である」と判断され、相続財産として課税対象となるケースが非常に多く、相続時に問題になることがあります。
今回は、名義預金・名義保険がなぜ問題になるのか、贈与税の時効との関係、税務署に発覚する理由、そして適切な対策について詳しく解説します。
1.名義預金とは?贈与税の時効は成立するのか
名義預金とは、「口座の名義人」と「実際の所有者」が異なる預金のことを指します。
たとえば、孫が名義人である預金口座に、祖父が毎年100万円ずつ、10年間にわたって合計1,000万円を入金していたケースを考えましょう。
一般的に、贈与税を申告しなかった場合、法定申告期限の翌日から6年(悪質な場合には7年)で時効を迎えるとされています。
そのため、「10年以上前に祖父からもらったお金だから、時効が成立しているはずだ」と考える方もいるかもしれません。
しかし、名義預金は生前贈与として贈与税の時効が成立することはありません。
なぜなら、税務署は「名義預金は被相続人の預金を相続人名義の口座で預かっていたという事実」と認定するため、そもそも贈与が成立していないと判断されるからです。
贈与が有効に成立するためには、民法第549条にあるように、「贈与する人の意思表示」と「贈与を受ける人の受諾」が必要となります。
たとえば、親が子供に内緒で子供名義の通帳を作り、そこに振り込んでいた場合など、口座の名義人がその存在を知らなかったり、自由に管理できる状態になかったりする場合は、贈与契約が成立していないとみなされます。この場合、その預金は実質的に被相続人の財産と判断され、相続税の課税対象となります。
また、贈与があったことを隠して時効になるのを待っていたなど「偽りその他不正の行為」があったと税務署に認定された場合は、時効期間が7年間に延長されます。
2.名義預金が税務署に発覚する理由
「名義預金は税務署にバレないだろう」と考える方もいますが、実際には高確率で発覚します。
名義預金が発覚する主な理由は、相続税の税務調査にあります。
税務調査では、税務署は被相続人やその親族の預金口座を閲覧する権限を持ち、過去10年間の取引履歴まで厳しく確認します。
具体的には、以下の点がチェックされます。
- 印鑑の確認: 通帳の印鑑と自宅にある印鑑を照合し、同じ印鑑が複数の通帳で使い回されていないか確認します。
- 入出金の確認: 被相続人の通帳からの出金日近くに、同額程度の入金が相続人や孫の通帳にないか確認します。
- 振込の確認: 被相続人の通帳から相続人や孫などへの振込がないか確認します。
- 保険の支払い: 被相続人の通帳から保険料が支払われている場合、その契約者が被相続人であるか、積み立て式の保険であれば解約返戻金が名義保険としてチェックされます。
- 不自然な口座開設: 口座名義人の居住地と異なるエリアの金融機関で口座が開設されていたり、口座名義人と届出印の所有者が異なったりする場合も疑われます。
- 資産取得時の資金源: 収入が少ないにもかかわらず高額な不動産などを購入した場合、その資金源が贈与ではないかと税務署から「お尋ね」が届くことがあります。
国税庁のデータによると、申告漏れ相続財産のうち現金・預貯金等が大きな割合を占めており、税務調査で名義預金が発覚する可能性は決して低くありません。
3.名義預金が発覚した際のペナルティ
相続税の申告期限後に名義預金の存在が発覚した場合、以下のような重いペナルティが課せられる可能性があります。
- 過少申告加算税: 申告額が本来よりも少なかった場合に課せられます。税率は10%〜15%ですが、税務調査の事前通知前に自主的に修正申告をすれば課されません。
- 無申告加算税: 期限までに申告をしなかった場合に課せられます。税率は5%〜20%(300万円を超える部分は25%〜30%)ですが、自主的に期限後申告を行えば税率が5%に下がります。
- 重加算税: 相続財産を仮装・隠ぺいしていたと判断された場合に課せられます。申告書を提出していた場合は35%、提出していなかった場合は40%と、最も税率が高いペナルティです。
- 延滞税: 納税が遅れたことに対するペナルティで、法定納期限の翌日から納付する日までの日数で日割り計算されます。税率は期間によって異なりますが、年2.4%〜14.6%程度です。
これらのペナルティは、自主的に修正申告や期限後申告を行うことで税率を抑えることが可能です。
4.名義預金とみなされないための対策
名義預金と判断されるリスクを避けるためには、以下の点を押さえることが重要です。
- 口座内のお金を名義人が自由に使えるようにする: 通帳やキャッシュカードなどを名義人に渡し、名義人自身が口座を管理できるようにします。
- 贈与契約書を作成する: 贈与契約は口頭でも成立しますが、贈与者と受贈者の合意があったことを客観的に証明するため、贈与契約書を作成することが強く推奨されます。契約書には、贈与日、贈与者・受贈者の氏名・住所、贈与財産、贈与方法などを記載し、署名と実印を押印すると良いでしょう。
贈与契約書については下記の記事をご参照ください。
- 銀行振込をして記録を残す: 銀行振込を利用することで、贈与者と受贈者の口座間で資金が移動した記録が残り、客観的な証拠となります。
- 必要に応じて贈与税を申告する: 1月1日から12月31日までの贈与額が合計110万円を超える場合は、贈与税を申告・納税することが大切です。これにより、贈与があったことを税務署に公式に認めてもらうことにつながります。
5.すでに名義預金をしている場合の対処法
もしすでに名義預金をしてしまっている場合は、以下の対処法が考えられます。
- 名義人の口座にお金を戻す: 名義預金の口座にあるお金を、本来の持ち主(被相続人)が名義人である口座に戻す方法です。これは、単に所有者の口座に戻すだけなので、贈与税はかかりません。
- 預金口座の名義を変更して贈与する: 一度名義預金の名義人を本来の所有者(被相続人)に戻した上で、改めて正式に贈与を行う方法です。この際、贈与契約書の作成や銀行振込を徹底し、年間110万円を超える贈与であれば贈与税の申告も行います。ただし、相続開始前一定期間内(2024年1月1日以降の贈与から段階的に最長7年)に相続人に対して行われた生前贈与は、相続税の課税対象に加算される「生前贈与加算」の対象となる点に注意が必要です。
- 生命保険に加入する: 名義預金のお金で保険料を支払い、生命保険に加入する方法もあります。被相続人が契約者・被保険者で、相続人を受取人とする死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」まで相続税が非課税になります。また、死亡保険金は受取人固有の財産であり、遺産分割協議の対象外となるため、迅速な資金確保にも役立ちます。
6.まとめ
名義預金は、被相続人が亡くなった際に相続財産とみなされ、相続税の課税対象となる可能性が高いものです。生前贈与が成立していると認められない限り、贈与税の時効は適用されません。
将来、残された家族が多額のペナルティを課される事態を防ぐためにも、生前贈与を行う際は、贈与契約書の作成、銀行振込による記録の残存、そして必要に応じた贈与税の申告といった適切な手続きを踏むことが非常に重要です。
名義預金の問題や相続税対策についてご不安な点があれば、相続税に詳しい税理士に相談することをおすすめします。