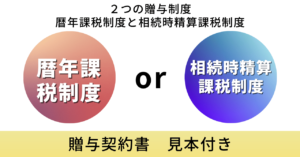「大切な財産を子や孫に引き継ぐ際、相続と贈与、どちらを選べば税負担を抑えられるのだろうか?」多くの方が抱くこの疑問に対し、一見すると贈与税の方が高く見えますが、実は計画的な生前贈与は相続税の節税に大きく貢献する可能性があります。
本記事では、相続税と贈与税の基本的な違いから、税率の比較、それぞれの特例・控除、そして具体的なシミュレーションを通して、どちらがよりお得になるのかを税理士の視点から詳しく解説します。この記事を読み終える頃には、ご自身の状況に合わせた最適な節税対策が見えてくるでしょう。
1.相続税と贈与税の基本:まずはそれぞれの仕組みを理解しよう
相続税と贈与税は、いずれも財産を受け渡す際に課される税金ですが、その仕組みや性質には大きな違いがあります。
1-1. 相続税とは?
相続税とは、亡くなった人(被相続人)から財産を相続した際に、その財産にかかる税金です。財産を受け取った相続人が国に支払います。
相続税の課税対象となるのは、「課税価格の合計額 - 基礎控除額」で計算される「課税遺産総額」です。基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で算出され、この金額以下であれば相続税はかかりません。
相続人は、被相続人との血縁の近さによって順位が定められており、配偶者は常に相続人となります。相続税の税率は、財産額に応じて10%から最高55%までの累進課税方式が適用されます。
1-2. 贈与税とは?
贈与税とは、個人から年間110万円を超える財産の贈与を受けた際に課される税金です。贈与は、財産を渡す側が生きている間に行うことができ、贈与する人とされる人(受贈者)の合意によって成立します。
贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」があります。
• 暦年課税: 1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた金額に課税されます。年間110万円以下であれば贈与税はかかりません。
• 相続時精算課税: 60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に選択でき、特別控除額2,500万円までが非課税となります。令和6年1月1日以降の贈与からは、この制度にも年間110万円の基礎控除が創設されています。
贈与税の税率は、相続税よりも高い傾向にあり、特に18歳以上の子・孫が父母・祖父母から贈与を受けた場合には「特例税率」が適用され、その他の贈与には「一般税率」が適用されます。
1-3. 相続税と贈与税、発生タイミングと課税対象の違い
| 違い | 相続税 | 贈与税 |
| 発生のタイミング | 被相続人が死亡したとき | 両当事者が合意したとき |
| 課税対象 | 基礎控除額を超える財産 | 年間110万円を超える財産 |
| 課税対象者 | 相続人 | 財産を取得した人 |
| 税率 | 贈与税より低い | 相続税より高い |
| 関係の有無 | 亡くなった人の相続人・受遺者のみ | 贈与者との関係を問わない(家族以外も可) |
| 申告期限 | 被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内 | 贈与した年の翌年の2月1日から3月15日まで |
2.税率だけを比較するのはナンセンス?:賢い節税の考え方
「相続税と贈与税の税率を比較すると、贈与税の方が高い」と感じる方が多いかもしれません。確かに同じ金額の財産を一度に引き渡す前提で比較すれば、贈与税の方が高くなります。しかし、この単純な比較だけでは「どちらがお得か」を正しく判断できません。
2-1. 同じ金額を一度に渡すなら贈与税の方が高い
例えば、1億円の財産を一度に渡すケースで比較してみましょう。
• 相続税の場合(法定相続人が子1人): (1億円 - 基礎控除3,600万円) × 30% - 700万円 = 1,220万円
• 贈与税の場合(親から成人した子への特例贈与): (1億円 - 110万円) × 55% - 640万円 = 4,799万5,000円
この例では、一度に全額を贈与すると贈与税の方が圧倒的に高額になります。
2-2. 「小分け贈与」で贈与税がお得になる理由
相続税は「全財産を一度に渡す」ことが前提となるのに対し、生前贈与は財産を「小分けにして渡す」ことが可能です。この「小分け」こそが、生前贈与を節税に有効な手段とする鍵となります。財産を複数回に分けて贈与を繰り返すことで、贈与税の税額合計を相続税よりも低く抑えることができます。少額の贈与であれば、贈与税の負担が相続税よりも小さくなるため、相続税が課税される方にとっては、贈与税を払った方が結果としてお得になる可能性が高いのです。これは、相続税の最高税率が適用される部分の財産を、より低い贈与税率で減らすことができるためです。
3. 具体例で比較!生前贈与が「お得」になるシミュレーション
ここでは、具体的な数値を用いて生前贈与の節税効果を見てみましょう。 前提条件: 総資産2億4,200万円、法定相続人は子ども2人(遺産分割は法定相続分に従う)と仮定します。
3-1. 相続で財産を一度に渡した場合
まず、生前贈与を行わず、総資産2億4,200万円を子ども2人で相続した場合の相続税を計算します。
1. 基礎控除額の計算: 3,000万円 + (600万円 × 2人) = 4,200万円
2. 課税遺産総額の計算: 2億4,200万円 - 4,200万円 = 2億円
3. 各法定相続人の法定相続分に応じる取得金額: 2億円 × 1/2 = 1億円
4. 子ども1人あたりの相続税額: 1億円 × 30% - 700万円 = 2,300万円
この場合、子ども1人あたり2,300万円、合計4,600万円の相続税がかかります。
3-2. 生前贈与を計画的に行った場合
次に、この親が生前に子ども2人にそれぞれ1,000万円ずつ生前贈与し(合計2,000万円)、残りを相続させた場合を考えます(子どもは18歳以上とします)。
1.贈与税の計算
年間1,000万円の贈与を受けた場合(特例税率)。
(1,000万円 - 基礎控除110万円) × 30% - 90万円 = 177万円。
子ども1人あたり177万円、合計354万円の贈与税がかかります。
2. 相続税の計算
総資産2億4,200万円から贈与分2,000万円を引くと、残りの相続財産は2億2,200万円。
課税対象となる財産: 2億2,200万円 - (3,000万円 + 600万円 × 2人) = 1億8,000万円
子ども1人あたりの相続税額: 1億8,000万円 × 1/2 × 30% - 700万円 = 2,000万円
3. 贈与税と相続税の合計額
子ども1人が支払う合計税額: 177万円 (贈与税) + 2,000万円 (相続税) = 2,177万円生前贈与しなかった場合の相続税額2,300万円と比較すると、子ども1人あたり123万円の節税効果が得られたことになります (2,300万円 - 2,177万円)。 このように、計画的な生前贈与は、最終的な税負担を大幅に軽減する有効な手段となり得ます。
4. 生前贈与を検討すべきケースとおすすめできないケース
生前贈与が有効な節税対策となる一方で、すべてのケースでメリットがあるわけではありません。ご自身の状況に合わせて検討することが重要です。
4-1. 生前贈与が有効なケース
生前贈与は、以下のような状況で特に有効です。
若く健康なうちに始める
贈与する人の年齢が若く、健康であるほど、計画的に何度も贈与を繰り返すことができるため、生前贈与のメリットが大きくなります。後述する「7年内加算」のルールを考慮すると、より早期からの対策が重要です。
賃貸不動産など収益性のある財産がある
不動産からの家賃収入がある場合、今後も財産が増え続け、将来的に相続税の負担が重くなる可能性が高いです。不動産を子に贈与すれば、贈与後の家賃収入はすべて子の財産となり、贈与者の相続財産には含まれなくなります。 ただし、不動産の贈与には高額な贈与税がかかる可能性があるため、相続時精算課税制度(最高2,500万円の特別控除、令和6年1月1日以降は年間110万円の基礎控除も併用可能)の利用も視野に入れると良いでしょう。
財産を引き渡す子・孫が多い
贈与税は、1人につき年間110万円までが非課税です。そのため、財産を引き渡す子や孫が多いほど、非課税の範囲で贈与できる金額が増え、短期間で大きな節税効果を期待できます。例えば、子3人、孫2人の合計5人に贈与する場合、年間550万円(110万円×5人)まで非課税で贈与が可能です。
4-2. 生前贈与に注意が必要なケース
生前贈与が必ずしも得策ではないケースもあります。
相続税がかからない場合
相続財産が相続税の基礎控除額以下の場合、そもそも相続税は発生しないため、節税目的での生前贈与は不要です。この場合、年間110万円を超える贈与をしてしまうと、無駄な贈与税を支払うことになってしまいます。
小規模宅地等の特例を適用したい土地がある場合
小規模宅地等の特例とは、被相続人の自宅や事業用の宅地を相続した場合に、一定の要件を満たせばその土地の相続税評価額を最大80%減額できる非常に節税効果の高い制度です。
この特例が適用できる土地については、毎年少しずつ持ち分を贈与するよりも、相続の際に一度に引き継ぐ方が得になる場合があります。贈与してしまうと、この80%減額の恩恵を受けられなくなるため、注意が必要です。
また、不動産の生前贈与には、不動産取得税や登録免許税、司法書士報酬などの費用が毎年かかることも考慮すべき点です。相続の場合は不動産取得税はかからず、登録免許税も低税率で済み、司法書士報酬も1回で済むため、コスト面でもメリットがあります。
5. 知っておきたい!相続税・贈与税の特例・控除制度
相続税・贈与税には、税負担を軽減するための様々な特例や控除が設けられています。
5-1. 相続税の節税に役立つ特例
- 配偶者の税額軽減: 被相続人の配偶者は、1億6,000万円または法定相続分相当額の多い方までは相続税がかからない制度です。
- 未成年者の税額控除: 相続人が未成年である場合に、相続税額から一定額を差し引ける制度です。
- 障害者の税額控除: 相続人が85歳未満の障害者である場合に、相続税額から一定額を差し引ける制度です。
- 相次相続控除: 今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続税を納めていた場合に、相続税額から一定額を差し引ける制度です。
- 贈与税額控除: 相続税額からすでに納めている贈与税額を差し引ける制度で、二重課税を防ぎます。
- 小規模宅地等の特例: 個人が一定の土地または権利を相続した場合に、土地の評価額を最大400㎡の80%まで減額できる制度です。
5-2. 贈与税の節税に役立つ特例
暦年贈与の基礎控除110万円以外にも、特定の目的に対する非課税枠が設けられています。
- 相続時精算課税制度: 60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で、最高2,500万円までが非課税となる制度(令和6年1月1日以降は年間110万円の基礎控除も併用可能)。
- 教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税: 30歳未満の子・孫が父母・祖父母から教育資金の贈与を受けた場合に、1,500万円までは贈与税がかからない制度。
- 結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税: 18歳以上50歳未満の子・孫が父母・祖父母から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合に、1,000万円までは贈与税がかからない制度。
- 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税: 子・孫が父母・祖父母から住宅を取得するための金銭の贈与を受けた場合に、省エネ等住宅で最高1,000万円まで、その他の住宅で最高500万円までは贈与税がかからない制度。
- 配偶者控除: 婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその購入資金の贈与が行われた場合に、基礎控除(110万円)に加えて最高2,000万円まで差し引ける制度。
- 特定障害者に対する贈与税の非課税: 特定障害者を受益者として財産を信託した場合に、最高6,000万円までは贈与税がかからない制度。
6. 生前贈与を成功させるための注意点
生前贈与による節税を確実にするためには、いくつかの重要な注意点を理解しておく必要があります。
6-1. 「7年内加算」のルールに注意
贈与者が亡くなる直前に相続税を減らす目的で行われた贈与を防ぐため、相続開始前一定期間内の贈与は、相続財産に加算され、相続税の対象となります。この期間は、令和5年度の税制改正により、令和6年1月1日以降の贈与から「3年以内」から「7年以内」へと段階的に拡大されました。このため、生前贈与は、贈与する人が若く健康なうち、できるだけ早い時期から始めることが大切です。
6-2. 「名義預金」「定期贈与」とみなされないための対策
税務署は、預貯金残高や入出金履歴などを調べており、贈与の申告漏れはバレることが多いです。申告漏れが発覚すると、本来の税額に加えて加算税や延滞税が課されます。
また、単に親が子ども名義の預金口座に毎年資金移動しているだけでは、「名義預金」と認定され、贈与が認められないリスクがあります。さらに、毎年一定の時期に一定の金額を贈与する「定期贈与」とみなされると、「あらかじめ贈与する総額が決まっていた」と判断され、一括贈与として高額な贈与税が課される可能性があります。
これを避けるためには、以下の対策が有効です。
- 贈与契約書を毎年作成する(可能であれば公証人役場で確定日付を取得する)。
- 贈与する時期や金額を一定にしない。
- 贈与後は、受贈者自身が通帳や印鑑を管理し、贈与の事実を認識していること。
6-3. 不動産の生前贈与にかかるコスト
不動産を少しずつ持ち分で贈与する場合、毎年不動産取得税(固定資産税評価額の3%)や登録免許税(固定資産税評価額の2%)がかかります。さらに、毎年司法書士への報酬(5万円~20万円程度)が発生するため、これらのコストも考慮に入れる必要があります。相続の場合はこれらの費用が大きく異なるため、慎重な検討が求められます。
7. まとめ:最適な対策は専門家への相談が鍵
相続税と贈与税のどちらがお得になるかは、保有する財産の状況、家族構成、そして将来の計画によって大きく異なります。一概に「生前贈与がお得」と断言できるわけではなく、相続税がかからない方にとって、贈与税を支払うことは無駄になる可能性もあります。
ご自身にとって最も効果的な節税対策を見つけ、最適な贈与額や時期を判断するためには、専門的な知識と経験が必要です。
相続や贈与に関するご不安やお悩みは、「税理士法人とおやま」までご相談ください。実績豊富な専門家が、お客様のご状況に合わせて最適な対策をご提案し、大切な財産を守るための総合的なサポートを提供します!