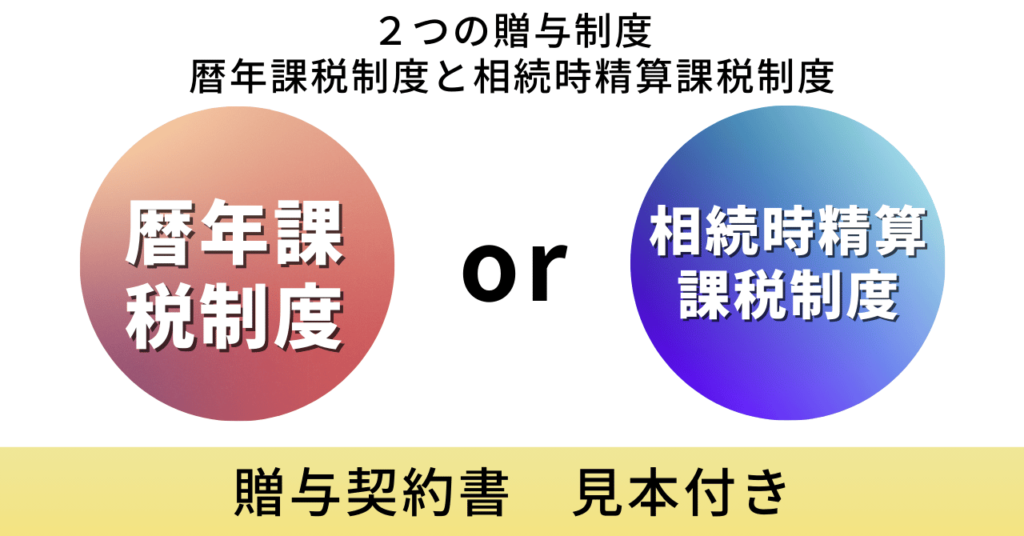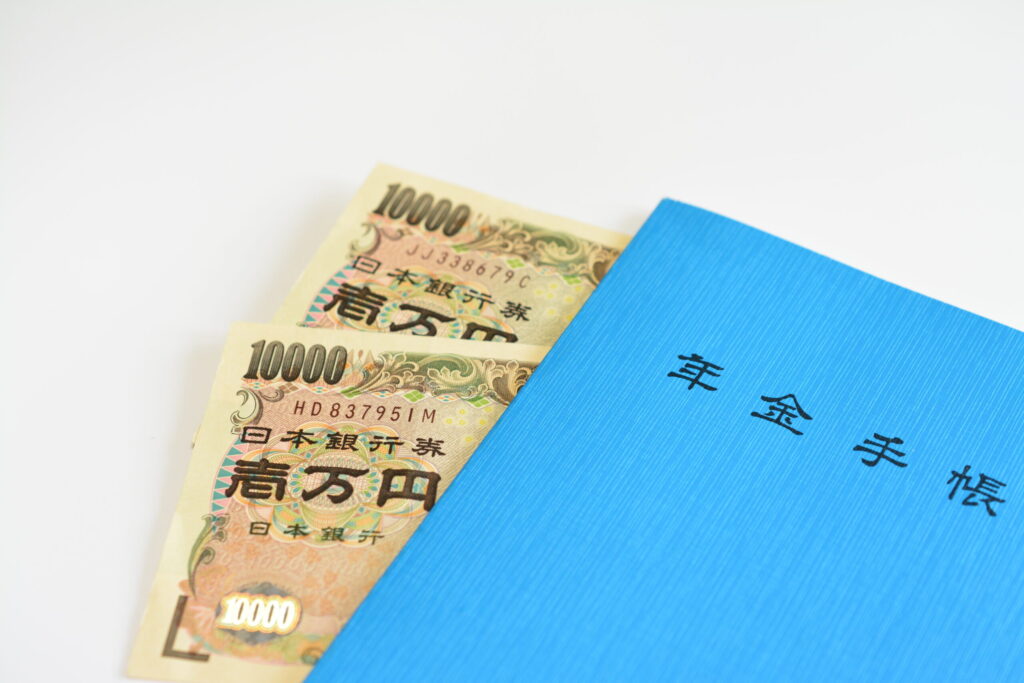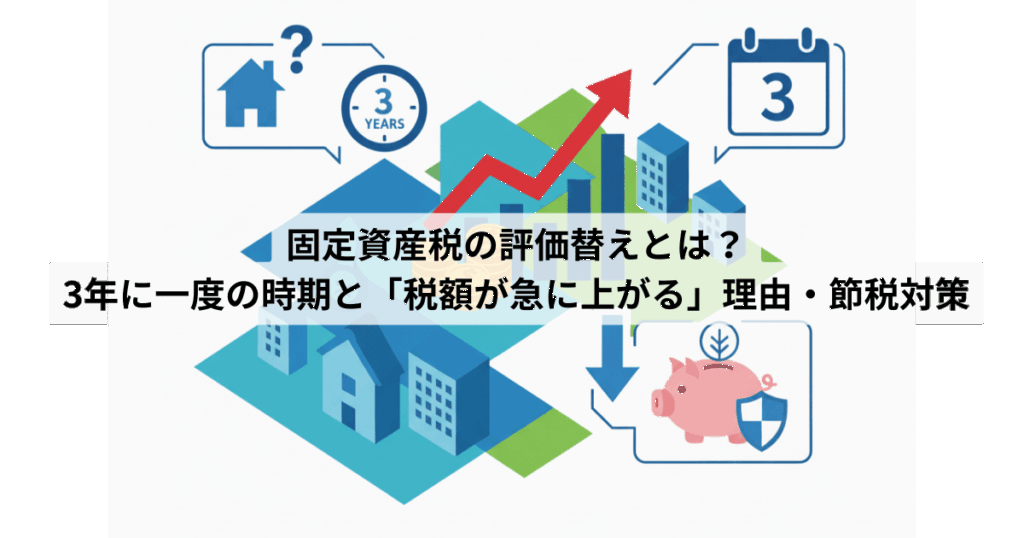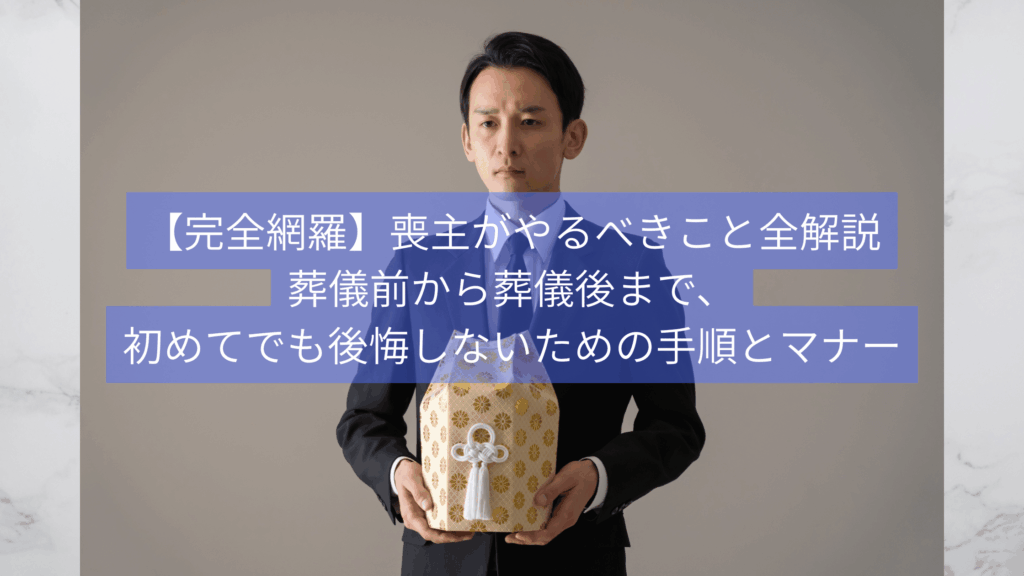
大切な方を亡くされた際、突然喪主という重責を担うことになり、「何をすべきか分からない」「責任重大で気が重い」と感じる方は少なくありません。葬儀に参列する機会はあっても、自分が喪主を務める経験は少ないはずです。
喪主は、故人様に代わって弔問客を迎え、葬儀を滞りなく進めるための中心人物(進行役)です。特に、葬儀の準備やマナーを事前に把握し、心の準備を整えておくことで、納得のいくご葬儀を執り行うことができます。
この記事では、喪主が務めるべき役割の基本から、葬儀前・当日・葬儀後まで時系列でやるべきことを詳しく解説します。

1. 喪主の基本:3つの役割と決め方
喪主が担うべき役割は多岐にわたりますが、主に以下の3つに集約されます。
- 葬儀の方針や内容の決定
- 遺族の代表者(連絡窓口・接客応対)
- お香典や葬儀費用の管理
喪主には、葬儀全体の内容を決定する決定権があります。費用やプラン、参列者の範囲、祭壇の装飾など、短時間で多くの判断を下す必要があります。
喪主の決め方
喪主には明確なルールはありませんが、一般的には故人の配偶者が務めます。
配偶者が高齢や体調不良で務められない場合は、血縁関係が近い順に、子ども(長男・次男、長女・次女)、故人の両親、故人の兄弟姉妹へと引き継がれるのが一般的です。最近では核家族化の影響もあり、配偶者や血縁者がいない場合は知人や友人が務めるケースもあります。
施主との違い
施主(せしゅ)とは、葬儀にかかる費用を負担する人を指します。かつては喪主と施主を明確に分けていましたが、現代では核家族化が進み、喪主が施主を兼任することがほとんどです。
2. 喪主がやるべきこと:ご臨終から葬儀前
ご臨終を迎えてからお通夜が始まるまでが、喪主にとって最も慌ただしい時期となります。
2-1.ご臨終時
| 喪主がやるべきこと | 備考 |
| 死亡診断書の受け取り | 死亡届とセット。役所提出や手続きで必要(葬儀社代行が一般的)。 |
| 病院での退院手続きと支払い確認 | 病院が主導で進めることが多い。 |
| ご遺体の搬送と安置先決定 | 病院の霊安室は短時間しか滞在できないため、速やかに搬送を手配。安置先は自宅または葬儀場の安置室が一般的。 |
2-2.葬儀前
| 喪主がやるべきこと | 備考 |
| 葬儀社の手配・打ち合わせ | 葬儀の規模(家族葬、一般葬など)や日程、プランを決定。見積もり内容を必ず確認する。 |
| 菩提寺・宗教者への連絡 | お通夜や葬儀で読経をしてもらうため、早めに連絡し日程を抑える。お布施の金額を確認する。葬儀社が手配をしてくれることが一般的。 |
| 死亡届の記入・提出 | 死亡の事実を知った日から7日以内に手続きが必要だが、葬儀社が代行するのが一般的。 |
| 訃報の連絡 | 親族や参列希望者へ、故人の名前、日時、場所、喪主の名前などを端的に伝える。家族葬の場合は、参列の辞退や香典辞退の意向を伝える。 参列者が確定したら、名簿を準備しておくと葬儀当日よりスムーズに進められます。 |
| 供花・供物の取りまとめ | 親族分の供花を取りまとめ、葬儀社に伝える。 |
| 遺影写真の準備 | 故人らしさが表れている、ピントが合った写真を選びましょう。 |
3. 喪主がやるべきこと:葬儀当日(お通夜・告別式)
葬儀当日は、進行の大半を葬儀社が担ってくれますが、喪主は遺族の代表として、挨拶や各種確認、参列者への対応に集中します。
3-1. お通夜と葬儀開始前(到着後)
喪主は、お通夜が始まる1〜2時間前には葬儀場に到着するのが望ましいです。
3-1-1. 式場の確認と司会者との打ち合わせ
- 弔電を読む順番や、供花(きょうか)の配置順を確認します。供花は故人と関係が深かった人のものから順に配置されます。
- 弔電が複数ある場合は、時間の都合上、読み上げるものを3〜5通程度選びます。
3-1-2. 僧侶への挨拶とお布施の準備
- 僧侶が到着したら、遺族の代表者として近くまで行き、簡潔に「本日はよろしくお願いいたします」と挨拶します。
- このタイミングで、切手盆などに乗せてお布施を手渡します。葬儀前に渡す時間がなければ、葬儀後でも問題ありません。
3-1-3. 参列者への対応
- 会葬者や弔問客を迎え、挨拶をします。
- 参列者から「ご愁傷様です」と声をかけられた場合、返答は「恐れ入ります」と伝えましょう。「ありがとうございます」のみの返答は絶対NGとされる場合があります。
3-2. 喪主の挨拶(最も重要な役割の一つ)
遺族の代表として行う挨拶は、喪主の最も重要な役目です。家族葬であっても、挨拶はマナーとして必要です。
| 挨拶のタイミング | 挨拶の場所と目的 |
| 通夜閉式の挨拶 | 読経・焼香終了後、通夜振る舞いに移る前。参列へのお礼と、翌日の葬儀日程を案内。 |
| 通夜振る舞いの挨拶 | 食事の開始前や終了時。故人との思い出話を聞かせてもらうよう促す。 |
| 告別式の終盤の挨拶 | 告別式終了後、または出棺の際。参列へのお礼と、故人が生前受けた厚意への感謝、今後の遺族への支援をお願いする。 |
| 精進落としの挨拶 | 食事の開始前や終了時。葬儀が無事終了したことへの感謝を伝える。 |
挨拶のポイントとマナー
- 長すぎないこと: 挨拶は緊張しやすいですが、内容は3分以内を目安に手短に話すことが推奨されています。
- メモの使用: 挨拶の内容を忘れることがあっても、内容を書いた紙やメモを見ながら話して全く問題ありません。
- 忌み言葉の回避: 不幸が重なることを連想させる重ね言葉(例:重ね重ね、ますます、再び)や、死や苦しみを直接的に表現する言葉(例:急死、生きていたころ)は避けるべきです。
| 忌み言葉 | 言い換え |
| 再び | 今一度 |
| 追って | 後ほど |
| 引き続き | これからも |
| 忙しい | 多用 |
| 次に | その後・新たに |
| 死ぬ | ご逝去・他界 |
| 生きていたころ | お元気だったころ・ご生前 |
| 急死 | 突然のこと・急逝 |
| 重ね言葉 | 言い換え |
| 重ね重ね | 深く・加えて |
| いろいろ | 多くの・さらに・もっと |
| 度々 | よく・しげく |
| 次々 | たくさん・立て続けに・休みなく |
| くれぐれも・重々 | 十分に・よく・どうぞ |
| ぜひぜひ | ぜひとも・ぜひ |
| ますます | もっと・一段と・よりいっそうの |
| みるみる | 見るまに |
| 近々 | 近いうちに |
| わざわざ | あえて・特別に |
| どんどん | たくさん |
| 日々 | 毎日 |
| つくづく | 心から |
3-3. 火葬〜初七日法要
葬儀・告別式後は火葬場へ移動します。
- 火葬場での待機時間: 火葬が終わるまで40〜90分程度(目安)の待ち時間があります。喪主は参列者に控室への案内をします。
- 収骨: 火葬が終わると収骨(骨上げ)を行い、故人のご遺骨は喪主が自宅に持ち帰ります。
- 繰り上げ初七日法要・精進落とし: 近年では、火葬の後に初七日法要を繰り上げて行い、その後、参列者に感謝とねぎらいの気持ちを込めて精進落としの席を設けることが一般的です。
4. 喪主がやるべきこと:葬儀後(金銭・行政手続きを含む)
葬儀が終わった後も、喪主の仕事は多岐にわたります。特に金銭や行政に関わる手続きには期限があるものも多いため、計画的に進める必要があります。
4-1. 費用精算と香典返し
4-1-1. 葬儀費用の精算
葬儀の翌日以降に葬儀社から費用の連絡があるため、期限内に支払いを済ませます。領収書は相続財産から控除できる葬式費用として必要になる場合があるため、必ず保管してください。
4-1-2. 香典返しの手配
- 香典返しは、香典をいただいた方へのお礼として贈る品物です。
- 一般的に、忌明け法要(仏式では四十九日法要)後、1か月以内に行います。
- 金額の相場は、いただいた香典の1/3〜1/2程度(半返し)が目安です。
- 品物は、「不祝儀が後に残らないように」という考えから、お茶や洗剤などの消えものを選ぶのがマナーです。
4-2. 法要と納骨の準備
4-2-1. 四十九日法要の準備
- 故人が亡くなってから49日目頃に行う重要な法要で、遺族が通常の生活に戻る節目とされます。
- 喪主は、日程や場所を決め、参列者への案内や会食(お斎)の手配、本位牌の準備を行います。
4-2-2. 納骨先の手配
- 納骨は四十九日法要時に合わせて行われるのが一般的です。
- お墓への納骨のほか、永代供養(納骨堂、樹木葬)や散骨など、近年増えている供養方法についても家族や親族と相談して決めます。
4-3. 各種行政・相続手続き
喪主は、葬儀後も多くの行政手続きや相続関連業務を担います。これらの手続きには期限が設けられているため、特に注意が必要です。
| 手続きの内容 | 期限(目安) |
| 年金受給停止手続き(厚生年金・国民年金) | 10日以内または14日以内 |
| 介護保険資格喪失届、国民健康保険の脱退手続き | 14日以内 |
| 準確定申告と納税(故人に所得税の申告義務がある場合) | 死亡後4ヶ月以内 |
| 相続税の申告・納税 | 死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内 |
| 生命保険の死亡保険金請求手続き | 死亡後3年以内 |
これらの手続きに加え、銀行口座の閉鎖、公共料金やクレジットカードの名義変更・解約、不動産の相続登記なども必要となります。特に、相続税の申告には専門的な知識が必要であり、期限が短いため、速やかな対応が求められます。

5.まとめ
喪主という重責は多くの場合突然訪れますが、その役割は葬儀当日の挨拶や対応だけに留まりません。葬儀プランの決定から、故人を偲び参列者を迎える当日の務め、そして葬儀後の行政手続きや相続といった現実的な処理まで、長期にわたり故人と遺族の双方に責任を負います。やるべきことは多岐にわたりますが、事前にその流れと役割を理解し心の準備を整えておくことこそが、慌ただしさの中でも故人への感謝を胸に、納得のいく最後のお見送りを実現する鍵と言えるでしょう。
税理士法人とおやまのご紹介
新宿区・豊島区を中心に相続に関するご相談を承っております税理士法人とおやまは、お客様の「もしも」の時の手続きを強力にサポートいたします。
葬儀後の煩雑な事務手続きの中でも、特に専門性が高く期限が定められているのが相続税申告です。当法人では、40年の経験と1000件以上の実績を持つ相続の専門家が、お客様の立場に立って丁寧にサポートいたします。
税理士法人とおやまの強み
- 豊富な経験と実績: 40年の経験と1000件以上の相続案件の実績があり、確かなサポートを提供します。
- 徹底した品質管理: 国税庁出身の税理士による品質管理を徹底しており、高度な専門性と節税対策を実現します。
- 不動産評価の強み: 不動産評価は税理士の知識と経験で大きく変わります。土地の形状や規模などを精査し、評価額を大幅に減額した解決事例もございます。
- 便利なアクセスと対応力: 平日9:00〜18:00の受付のほか、事前にご予約いただければ土日夜間にも対応可能です。遠方にお住まいの方でも、電話やWeb面談で安心してご相談いただけます。
相続税申告はもちろん、贈与税申告や、将来の税負担を軽減するための生前対策(相続税対策)など、幅広いサービスを提供しております。
相続に関するご不安や、「相続税がかかるかどうか知りたい」といった疑問をお持ちの方は、ぜひお気軽に税理士法人とおやまの無料相談をご利用ください。