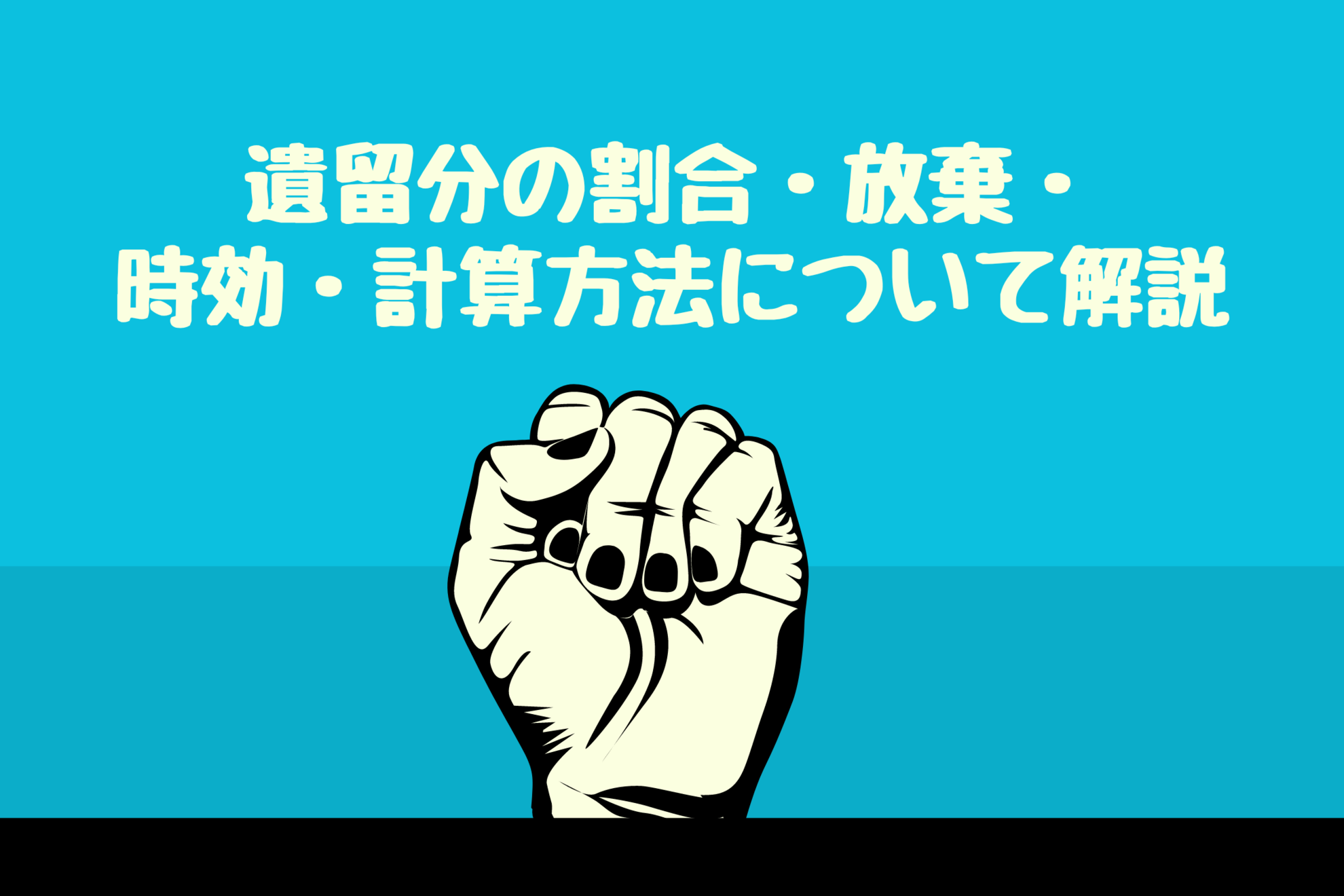遺留分とは、配偶者や子供など、一定の相続人が最低限保障される相続財産の割合のことです。遺言書があっても、この権利を奪うことはできません。
なぜ遺留分が必要なのでしょうか?それは、家族の生活の安定を図り、相続によって誰かが不当に損害を受けることを防ぐためです。
この解説では、遺留分の基礎知識から、計算方法、改正点、そして遺言書との関係性まで、わかりやすく解説していきます。
相続について、少しでも不安に感じている方は、ぜひご一読ください。
遺留分とは何か – 基礎知識の解説
遺留分とは、法定相続人(配偶者、直系卑属(子・孫など)、直系尊属(親・祖父母など))が、遺言や相続分協議によって自分の取り分が減らされても、最低限保障される相続財産の割合のことです。
なぜ遺留分が必要なの?
遺留分制度の目的は、相続人が遺産を失うリスクを減らし、生活の安定を図ることです。この制度により、被相続人が遺言によって特定の人や団体に全財産を譲り渡してしまうことを防ぎ、遺族が最低限の生活資金を確保できるようにします。
また、遺留分制度は家族間の不公平を防ぐためにも機能します。
例えば、遺言によって一部の相続人だけが優遇され、他の相続人が全く遺産を受け取れないという事態を避けるためです。
遺留分の割合の算定方法
遺留分の割合は基本的に法定相続分の半分となります。
法定相続分とは以下の割合のことをいい、相続人が誰かによって割合が異なっていきます。
法定相続分
配偶者と子供が相続人のとき
配偶者1/2 子供1/2
配偶者と親が相続人のとき
配偶者2/3 親1/3
つまり、遺留分の割合は以下のようになります。
配偶者と子供が相続人のとき
配偶者と子供※の遺留分 1/2 × 1/2 = 1/4
配偶者と親が相続人のとき
配偶者の遺留分 2/3 × 1/2 = 1/3
親※の遺留分 1/3 × 1/2 = 1/6
※子供や親の数が複数人の場合は均等にわって計算します。
例:子供が2人の場合は 1/4 × 1/2 = 1/8
遺留分と法定相続分の違い
遺留分
意味: 特定の法定相続人(通常は近親者)が受け取るべき最低限の相続財産の割合。遺言でこれを奪うことはできません。
目的: 近親者が最低限の生活基盤を失わないように保護すること。
割合: 法定相続分の1/2(直系尊属のみの場合は1/3)
法定相続分
意味: 民法に定められた遺産分割の目安となる割合
目的: 遺産を公平に分配するための基準
割合:
配偶者と子供の場合: 配偶者1/2、子供1/2
配偶者と親の場合: 配偶者2/3、親1/3
配偶者と兄弟姉妹の場合: 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4。
要するに、遺留分は遺言であっても削減できない最低限の相続財産の保護のために存在し、法定相続分は遺言がない場合の相続財産の分配の基準となるものです。
遺留分の改正点
従来は、遺留分を侵害された場合、具体的な財産を請求する「遺留分減殺請求」という方法が取られていました。しかし、この方法では、不動産などの分割が難しく、相続人間の争いが長引く原因となっていました。
改正後は、遺留分を侵害された相続人は、侵害された分の金額を金銭で請求できる「遺留分侵害額請求」が原則となりました。これにより、遺産の分割が簡素化され、相続手続きがスムーズに進みやすくなりました。
遺留分請求権の時効期間
遺留分請求権には、時効が設定されています。つまり、一定の期間内に請求を行わないと、その権利を失ってしまうということです。
時効の種類と期間
遺留分請求権には、大きく分けて2つの時効があります。
1.通常の時効(1年)
遺留分を侵害されていることを知った時から1年以内に請求を行わない場合、時効によって消滅します。
例えば、遺言の内容を知って自分の遺留分が侵害されていることに気づいた場合、そこから1年以内に請求手続きを進める必要があります。
2.除斥期間(10年)
相続開始から10年が経過すると、遺留分を請求する権利は、知っていたかどうかを問わず、消滅します。
例えば、相続が発生したことを知らずに10年が経過した場合、たとえ後に遺留分を侵害されていることに気づいたとしても、請求できなくなります。
時効の進行は、原則として中断することはできません。ただし、裁判手続きを開始するなど、特定の行為を行うことで、時効の進行を一時的に停止させることができる場合があります。
遺留分の計算方法 – 簡単に理解する
遺留分の計算は、大きく分けて以下の3つのステップで行います。
1.遺留分の基礎となる財産の算出
相続開始時の財産に、生前贈与などを加え、債務を差し引いた金額を算出します。
2.総体的遺留分の割合(相続人全員が合わせて相続できる最低限の財産の割合)の決定
相続人の構成によって、遺留分の総額が決まります。
3.個別的遺留分(総体的遺留分を、各相続人が自分の法定相続分に応じて受け取れる割合)の計算
総体的遺留分を、各相続人の法定相続分に応じて配分します。
具体的な計算方法
ステップ1:遺留分の基礎となる財産の算出
相続開始時の財産: 現金、預金、不動産、有価証券など、被相続人が亡くなった時点での全ての財産を評価します。
生前贈与: 相続開始前の1年以内の贈与は全額、相続人への特別受益(婚姻や養子縁組のための贈与など)は10年以内のものが加算されます。
債務: 借金などの債務は、財産から差し引かれます。
ステップ2:総体的遺留分の割合の決定
配偶者と子: 相続財産の1/2
配偶者と直系尊属(父母など): 相続財産の1/2
直系尊属のみ: 相続財産の1/3
ステップ3:個別的遺留分の計算
法定相続分による配分: 総体的遺留分を、各相続人の法定相続分に応じて配分します。
例: 配偶者と子が2人の場合、配偶者は1/2、子はそれぞれ1/4が法定相続分です。総体的遺留分が1/2の場合、配偶者は1/4、子はそれぞれ1/8が遺留分となります。
計算例
例: 被相続人の財産が1000万円で、配偶者と子が2人の場合
基礎となる財産: 1000万円(生前贈与や債務がない場合)
総体的遺留分: 1000万円 × 1/2 = 500万円
個別的遺留分:
配偶者: 500万円 × 1/2 = 250万円
子それぞれ: 500万円 × 1/4 = 125万円
遺留分の放棄
遺留分の放棄とは、法定相続人(通常は配偶者や子供など)が自分の遺留分を手放すことを指します。遺留分の放棄が出来るのは、遺留分権利者(本人)のみです。
他の法定相続人が代わりに申し立てをすることはできません。
遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要となります。
遺留分権利者が 遺留分を放棄したい旨を、家庭裁判所に申立てます。裁判所は、申立ての内容が適法であるかなどを審理します。審理の結果、問題がなければ、家庭裁判所は遺留分の放棄を許可する決定を下します。
遺留分の放棄を一度行うと、原則として取り戻すことはできませんので、放棄手続きをする際には慎重に行いましょう。
似たような言葉で、「相続放棄」があります。
相続放棄とは相続そのものを放棄することですが、遺留分放棄は、相続権は残したまま、遺留分という権利だけを放棄することです。
直系尊属と兄弟姉妹の権利
遺留分は、相続人が最低限保障される相続財産の割合ですが、相続人の種類によって権利の内容が異なります。
直系尊属(父母、祖父母など)
遺留分の権利あり: 直系尊属は、配偶者や子と同様に遺留分の権利を有します。
割合: 法定相続分に応じて、遺留分の割合が決定されます。配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者が1/3、直系尊属が1/6の割合で定められます。
兄弟姉妹
遺留分の権利なし: 兄弟姉妹は、遺留分の権利を有しません。
理由: 兄弟姉妹は、すでに独立して生活していることが多く、遺留分がなくても生活に困ることは少ないとされているためです。
なぜ兄弟姉妹には遺留分がないのか?
兄弟姉妹に遺留分がない理由としては、以下の点が挙げられます。
独立性: 一般的に、兄弟姉妹はすでに独立して生活しており、親からの経済的な援助を必要とすることは少ないです。
血縁の遠さ: 直系尊属に比べると、兄弟姉妹は血縁関係が遠いため、相続における保護の必要性が低いと考えられています。
代襲相続: 兄弟姉妹の子(甥や姪)は、親(兄弟姉妹)が亡くなっている場合に、代襲相続人として相続の権利を取得することができます。
遺留分と遺言書の関係性
遺言書があっても遺留分は保障される
遺言書を作成した場合でも、遺留分を有する相続人は、遺言書の内容にかかわらず、最低限の遺留分を請求することができます。これは、遺言書が全ての相続人の意向を完全に反映しているとは限らないため、法的に最低限の保障が設けられているためです。
遺言書で遺留分を侵害した場合
もし、遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、遺留分を有する相続人は、その侵害された部分について、裁判所に請求することができます。裁判所は、遺言書の内容を一部変更したり、遺留分相当額の支払いを命じたりする判決を下すことがあります。
遺言書を作成する際の注意点
遺言書の内容が、配偶者や子の遺留分を侵害しないように注意する必要があります。だからと言って遺留分を侵害している遺言書を書いてはいけない訳ではありません。相続人間で合意が取れているのであれば、自由な遺言を書いてしまっても構わないのです。
まとめ
今回は遺留分について紹介いたしました。遺留分は、相続において非常に重要な制度です。遺言を作成する際や相続が発生した際に、必ず理解をしておくことが大切です。
もし、相続のことでお悩みでしたら、税理士法人とおやまにご相談ください。